- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 対人関係
沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

「さようなら」と小さく私は呟いた(2)
2025/11/06
私はびっくりした。イベントをするのに、3,500円が高額だという意識はなかった。「今頃、無料の演奏会もありますからね。」
…そうか。ピアノコンサートでは人を集められないのか。
では、どうすれば、いい?
もう、これは。私を全面に出して、私と過ごす90分なりに価値を感じてくれる人を集めるしかない、そう思った。
私の64年をどんなふうに語ろう?
10年ホームページでお世話になっている、リウムスマイル!の穂口さんとの30分無料相談が、大きなヒントとなった。
14までは、私、ピアノで自分の感情を表現していた。
14ぐらいから、ピアノの先生と解釈が合わなくなって。ピアノを弾くのが苦しくなった。
それとともに。私は書くことへと移行していったのだった。
17の歳には、私は全くピアノを弾かなくなり、書くことのみになった。
言葉をつらつら書き連ねていた、14、15、16、17、18、19、20、21、22。
22の歳には、自分の書いたものが醜い、と思ってしまった。
誰にも向かわない言葉。誰とも繋がっていかない言葉。
蛇がトグロを巻くように。私の言葉は、どこへも向かわないで、ただ、自分の気持ちを吐露しているだけのもので。
そんな「醜い」言葉を、生み出すことに疲れてしまった。
私は。一旦、書くことをやめようと思った。
もし、書くとすれば。誰かと繋がっていく、誰かに語りかける言葉を、と思った。
…そこまで語った私に。穂口さんは「そのところが聞きたい」と言ってくれた。
タイトルも「弾くこと、書くこと、対話すること」でいいやん、と言われた。
そうか、と思った。副題をつけて「弾くこと、書くこと、対話すること〜ピアノとともに振り返る、私の64年〜」とした。
誰が私に言えるだろう 私の命がどこまで届くかを。〜岡田満里子のエッセイ「ぼくを見つけて」〜
2018/12/25
CAP(Child Assault Prevention)〜大人セミナー〜
2017/02/26
内容の無い会話をどれだけ続けることが出来るか
2017/02/13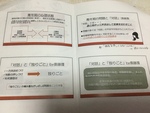
-
 読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休






















