沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。
あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。
カテゴリーごとに選べます。
呼吸法
苦しみは根っこに降ろす〜浅田慈照尼の法話「楽に生きるー晴れ、時々曇りー」〜
2019/07/09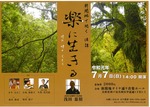
7月7日、15時。神戸・新開地のダイヤ通り音楽ホールにて、浅田慈照さんの、この地での3回目の法話がありました。
続き
浅田慈照さんは、高野山総本山金剛峯寺の布教師。
大学生であった19歳の時に、弘法大師空海に興味を持ち、高野山で出家得度、と「プロフィール」にありました。
18歳まで「頑張る」人生だった、と。努力して、努力して…が好きだった、と話し始められました。
けれど、弘法大師の道は「ラクしてラクする道」だと言われた、とのこと。
科学は「死んだら終わり」だけれど、仏教は死んだらあの世があると信じている。
死んだ先の世界があると信じるのも勝手。それぞれ個々人に任されている。
逝って帰ってきた人はいないのだから、どう思うのも勝手。
あの世があるとイメージしている方が、私としてはラク。
ああ、そうか…。何が正しいか、ではなく、どんな風に考えることが自分にとって生きやすいか、という指標に基づいた「楽に生きる」。
以下、慈照さんの言葉を拾っていきます。
呼吸法
ブッダは呼吸、ブッダは歩み〜ティク・ナット・ハン著『仏陀の<呼吸>の瞑想』〜
2019/06/07
今春、ゲシュタルト仲間であるともこさんからの紹介で、「Zoomでサンガ」という集いに参加するようになりました。
続き
それは、二週間に一度ぐらいのペースで、ほんの40分間の穏やかな時間。
ティク・ナット・ハン師(ヴェトナム生まれの禅僧)の『仏陀の<呼吸>の瞑想』(野草社)の一節を、誰かが読み、そのあと、感じたことを各々がシェアする時間。
私もそのテキストを手にしてみました。
「いったん止まって、息をしましょう」と題された「序」(?)の部分に、次のような文章がありました。
“私が住むプラムヴィレッジには、蓮池があります。蓮は泥なしには育ちません。大理石に蓮を植えるわけにはいかないのです。蓮の花が開くためにはどうしても泥が必要であり、理解と思いやりが生まれるためには苦しみが欠かせません。苦しみを抱擁し深く観つめるとき、私たちはそこから多くの学びを得ることができます。
仏教では、「ブッダに帰依する(よりどころとする)」という表現をよく使います。このブッダとは、どこか遠いところにいる人物のことではなく、私たちの内なる気づきと集中と洞察のエネルギーのことです。
私たちは思いやりの種を心のなかに持っています。だれでもときには理解や共感を発揮できるときがありますが、そのエネルギーは自分自身のなかから生まれます。これが内なるブッダのエネルギーです。ブッダはつねにあなたとともにあり、望めばいつでも触れられるところにいるのです。
いつでも、どこにいても、ブッダに触れられる方法のひとつ、それが呼吸です。”(pp.18-19)
蓮の花が泥なしに生まれないように、苦しみなしには、理解と思いやりが生まれない…。
まず、その一節が心に染みました。とはいえ、余りに苦しみが大きいとき、人はどうやってそれに耐えるのか?
関連エントリー
-
 読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休






















