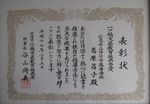- ホーム
- Works 1998〜2005 授業研究(高校・国語)に関する論文
Works 1998〜2005 授業研究(高校・国語)に関する論文
2017/05/05
(3)高等学校国語科における主題単元の実践(2000年)
1997年度紀要論文において、高等学校国語科における主題単元の必要性の考察及び私案を明らかにした。1998年度紀要論文では、それらを踏まえて新たに創造した単元(1998年度1学期実践)の成果と課題を通して、主題単元を成立させるための要件を考察している。
本論稿では、まず、Ⅰにおいて、1997年度紀要論文所収の単元構想から授業検証を経て、1998年度に完成した単元一覧(カリキュラム)を掲げ、その特徴を説明する。
さらに、Ⅱでは、1998年度実践中最も成果が上がったと考えられる、2学年における「単元 社会—職業から日本の家族や社会を考える」を取り上げ、分析と考察を加える。
Ⅰ 1998年度単元一覧(カリキュラム)
1997年度紀要論文において提示したカリキュラム編成原理に大きな変更点はないが、参考までに再度掲げておく。
<カリキュラム編成原理>
①年間カリキュラムをすべて主題単元で構 成する。
②学習者が学ぶべき認識の対象領域を、「自己」「言葉」「社会」「自然・文化・科学」「人間(生き方)」の5領域とし、1年間で扱う主題単元数は、認識の対象領域各1、合計5つとする。
③認識の対象領域は、「自己」「言葉」「社会」「自然・文化・科学」「人間(生き方)」の順に取り上げる。
④3年間とも、その5つの認識の対象領域を同じ順序で取り上げる。その際、同じ認識領域でも、問題に対する切り込み方を変えて主題を設定し、3年間での系統性を図る。
⑤各単元で育成する言語能力の明確な位置づけをする。
これにしたがって創造した単元一覧(カリキュラム)は次の「表1」のとおりである。
(表1)
この単元一覧(カリキュラム)には次のような特性がある。
1 教材数及びジャンル
一つの単元に付き、原則として教材は3つ用意した。(1つの教材が比較的長いものの場合、授業時間の関係上、教材数を2つにした。)それは二者の比較より三者の比較の方が、テーマに対する認識に奥行きや深みを生むことが可能であると考えたからである。また、教材の組み合わせも、文学作品と説明的文章を組み合わせることを原則とし、ジャンルが多岐に渡るよう配慮した。
2 発達段階に基づいた「認識内容の指導目標」の設定
認識対象領域ごとに、発達段階に基づく「認識内容の指導目標」を次のように設定した。
<1 自己>
第1学年では、第二次反抗期を過ぎてはいるもののまだ完全に脱し切れていない発達段階であることを考慮して、「大人と子どもの境界」について取り上げ、「好奇心」「追求心」といった「子ども性」は大人になっても必要であることを認識する。その上で第2学年では、しなやかな自己を育んでいくために自己を個性的に捉え、意識的に自己理解する必要性を認識する。第3学年では「孤独」を正面から取り上げ、自己を育むには自己受容・自己変革のバランスを取ることが必要であることを認識する。
<2 言葉>
第1学年では、まず言葉遊びの楽しさを味わい、日常の自分自身の言葉を振り返ることで、表現の可能性を認識する。第2学年では、もう少し言葉と人間の関わりについて深く考え、言葉とは人間の認識手段であり、認識方法でもあることを認識する。そのような言葉への認識の上に立って第3学年では、どんなものからでも材を取ってイメージ豊かに表現していくことが可能であり、そういった中で言葉の使い手としての力量が培われていくことを認識する。
<3 社会>
第1学年では、「自己」との関連で、家族の中でも親子関係に焦点を当てて、家族の有りようや社会の有りようを考えると共に、親からの自立とは何かについて認識する。特に親子関係に悩んできた学習者にとって、解決の糸口となる認識が育めるよう配慮した。第2学年では 進路選択の時期にぶつけ合わせて、職業を通して自分と社会との関わりを考え、自分なりの職業観を持つことを目標とした。特に親の仕事の聞き書きを通して、親を一面的にしか見てこなかったことに気づかせ、自分自身の生活が何によって支えられているかを認識することが必要であると考えた。第3学年では、高等学校終了後の長い人生を考え、望ましいパートナーシップを模索する手がかりをつかむことを目標とした。
<4 自然・文化・科学>
近代科学の発達とその課題について考えるのに、第1学年では環境問題を考える視点として生態系循環について認識することを意図した。第2学年では「文化」について取り上げ、個人の主観下にあると思われる時間感覚・空間感覚といったものが、文化的影響を受けていることを認識し、主観と客観がどのような関係にあるのかについての認識を深める。第3学年においてこれまでの近代科学の発展と現時点での課題を認識し、今後の方向性を探る手がかりを掴むことを目標とした。
<5 人間(生き方)>
各学年の最後に、人間とは何かを考え、生き方を模索する認識対象領域を設定している。第1学年では悩みに対する対応の仕方から人間の生き方を考え、第2学年では「所有」という問題を通して、どのような生き方を選択するのかを考える。第3学年では他者との関わりを育むことで自己疎外状況からの脱却方法の手がかりを掴むことを目標とした。
総じて、第1学年では日常の身近なことから主題に取り組み、第2学年では自分自身に関わりつつ、もう少し広い視野に立ち、ものごとに対する認識を深められるような課題設定をした。第3学年では、明確な結論を出すことを目標とせずに、学習者各人が今後の人生での課題が設定できることを意図した。
3 発達段階を考慮した「認識・表現方法の指導目標」の設定
各単元の各教材で「認識・表現方法の指導目標」を立てる際、3年間の発達段階を考慮して次のような点を配慮した。
(1)扱うジャンルは小説・ショートショート・詩・随想・論説・聞き書き・報道文であるが、そのジャンルのものを初めて取り上げる時には、ジャンル特性を捉える。
(2)論説・評論文・随筆等において、「論理展開・論理構造」及び「表現」についてはその作品特性に即して中心に据える項目を設定する。同様に小説や詩においても作品特性に即して重点課題を変える。
(3)前述の作品特性については、比較的容易に捉えることのできる教材を第1学年及び学年初めの単元に配置した。したがって第3学年においては比較的難易度の高いものが配置されている。但し、認識を深めるのに有効と認め、また学習活動との関連で比較的平易な教材を配置している場合もある。
このカリキュラムを「認識・表現方法の指導目標」の観点から捉えると、「表2」のとおりである。なお、「認識・表現方法」として指導すべき能力については、既に1997年度紀要論文で提示しているが、今回一覧表にまとめるにあたって「論説・評論文系統の場合」と「小説・詩系統の場合」を併記して示した。
(表2)
4 発達段階を考慮した「学習活動」の設定
発達段階を考慮した「学習活動」を次のように設定した。
(1)疑問点を出し合い、それについての意見交換を行う「グループ討論」を数多く設定した。
(2)すべての単元に、単元のまとめとして、教材相互の比較を行い、その後「単元のまとめの文章」を書くことを課した。一学期実施の単元「自己」「言葉」については、三段落で書くこと及び段落の柱を指示したが、字数制限は設けなかった。二学期実施の単元「社会」においては800字の意見文、「自然・文化・科学」においては800字の随想、三学期実施の単元「人間」については800字の小論文を課した。文種を変えたのは、様々な文体に慣れるためである。また800字の文章を書かせたのは、形式段落と意味段落を一致させて三段落構成で書く基礎を身につけさせたかったためである。
(3)「単元のまとめの文章」以外にも単元によっては教材から学んだことを踏まえ、詩を作る、随想を書く、聞き書きを書く、という学習活動を設定した。
Ⅱ 1998年度実践「単元 社会—職業から日本の家族や社会を考える」
1998年度実践中、最も成果が上がった考えられる、第2学年における「単元 社会—職業から日本の家族や社会を考える」を取り上げる。この単元は1997年度実践と同一テーマであるが、1997年度実践の課題を克服するため、教材及び学習指導の流れを変えたものである。
1 単元設定の趣旨
1998年度実践と1997年度実践を比較するに当たって、両者に共通する単元設定の趣旨を掲げておきたい。
単元設定の趣旨
「個」が前提とならない日本社会の問題を、就労の観点から捉える。経済的自立・社会的自立・精神的自立の根底となる職業を、就労形態と就労内容の両面から考え、自分にとって職業とは何を意味するかを考える。
2 1997年度実践の振り返り
(1) 教材、学習指導目標及び授業の流れ
1997年度の実践の教材、学習指導目標及び授業の流れは以下のとおりである。教材特性及び単元の構造については既に1997年度紀要論文で提案している。
教材
①「なぜ人は仕事を…」(『寄りかかっては生きられない—男と女のパートナーシップ』千葉敦子著・光風社出版・1989年)(論説)
②女性の就労形態に関するデータ(『女性のデータブック第2版』井上輝子・江原由美子編・有斐閣・1995年)(『家族データブック』久武綾子他著・有斐閣・1995年)
③「97今華躍るひろしま—100人の女性たち」(瀬川志保美編)から各自3編
学習指導目標
1 それぞれの教材から、仕事を通した、どのような生き方が書かれているかをつかむ
2 自分の職業観を見つめ直す
3 就労のあり方が、日本社会のあり方とどう関係するか考える
授業の流れ
第1次 単元に入る前のテーマに関する設問
第2次 教材①
第3次 教材②
第4次 教材③
第5次 単元のまとめ—意見文創出
第6次 意見文の相互批評及び自己批評、授業の振り返り(「単元 社会」の授業についての感想)
(2)1997年度実践の成果と課題
1997年度の「単元 社会」の実践については、既に1998年度紀要論文において、1年生の成果と課題をまとめている。その際、「教材を学習する前の、学習者のテーマに対する認識状況」と「単元のまとめとして書かれた意見文」に見られる認識状況及び「学習後の『単元 社会』の教材内容及び学習方法についての感想」を比較することで学習者の認識の変容という目的が達成できたかどうかを確認し、その原因を考察した。今回、2年生の成果と課題を考察するにあたって、同様に学習者の学習前と学習後の認識状況の比較を行うこととする。
なお、1997年度「単元 社会」の実践は、前記のカリキュラム編成原理の④に基づいて第1学年から第3学年の各学年で行ったものであるが、学習者にとっては各学年とも初めての単元学習であり、「社会」という認識対象領域の学習も初めてのものであった。したがって、今回取り上げる2学年の発達特性はカリキュラムに即して第1学年からの学習を積み上げた結果ではない。上記の限定された条件下で捉えられる特性と問題点であることを付記しておきたい。データはすべて2年7組1クラス40名についてのものである。
1)教材を学習する前の、学習者のテーマに対する認識状況
学習者の学習前の認識状況は、教材に入る前に書いた「『職業を持つこと』について、いま、あなたが考えること」に見ることができる。回答数37中、仕事の目的として「生活のため」をあげた者が一番多く17名であった。しかし、それだけでは満たされないためか、「生きがいになるような仕事に就きたい」「自分に合った仕事に就きたい」という将来の職業に対する希望を挙げる者が16名いた。一方で「責任がかかるので大変」といった不安も5名見られた。
2)単元のまとめとして書かれた意見文に見られる、学習者の認識状況
3つの教材を学習した後に「自分にとって職業とは何を意味するか」をテーマに800字の意見文を書かせた。そこから読みとれる学習者の「職業観」及びその職業観を支える「根拠」に着目して、学習後の到達地点を考察する。(回答数36)
「自分にとって職業とは何を意味するか」というテーマに正面から応えようとしたものが16名いたが、その中でごく常識的に「生活の糧を得るためと社会とのつながりからの充実感」を挙げたものが4名、自分の中で未整理であるため、挙げた項目がわかりづらいもの(「お金をもうけること+お金を使って家族を守る・自分を磨く」「充実感等得られるが、何かを犠牲にしているからこそ人生を豊かにするもの」)が2名、「自分自身を成長させる」や「人生を幸せにする」など理想的一面のみを取り上げたもの8名、昨今の就職難状況を反映して、どのような仕事に就きたいかより結果として「個人個人の能力にあった仕事」に就いていると見なすべきではないのかというものや「生きる営みの一部」として、私生活とのバランスを崩さずやっていきたいといった、少し冷めた見方をするものが2名あった。
「職業選びに関するもの」は15名見られたが、「自分に合った生きがいとなるような仕事に就くべき」「『やりたい仕事』に就くことが大切」など、理想を追求するものばかりだった。
「仕事への対し方に関するもの」は5名見られたが、「どんな仕事でも自分のやり方を見つけ、それに誇りを持つことが大切」という価値ある意見は1名で、残り4名は就職難状況の反映か、「生きていく(生活)ために職業を持つ」「望んでない職業でも新しい能力をそこで発見し、自分らしく生きたい」といった控えめな意見であった。
総じて理想追求に偏った傾向にあり、教材は理想をより明確にする働きをしたものの、多面的なものの見方や認識の深まりには至らなかった。そのことは、何をその意見の根拠にしたか、という点にも見ることができる。意見の根拠として用いられたものは教材の中では教材3が最も多く8名いたが、教材以外からのもの12名、明確な根拠なしが8名という結果だった。この中で教材2を用いたものが一つもなかったことは、社会全体を視野に入れて、その中での位置づけを確認するという視点に立っていないことがうかがえる。
3)単元学習における、学習者の教材内容及び学習方法に対する感想状況
学習後の「単元 社会」の教材内容及びが学習方法についての感想を考察する。感想結果は次のように分類できる。(回答数34)
感想の分類
A 教材内容に関するもの…28
1 実感がわかなかった…6
2 今まで自分が持っていなかった新しい知識を得た…22
①いろいろな考え方を知った—7
②自分自身でじっくり考えた—6
③自分自身の意識が問われることに気づいた—1
④社会の厳しさがわかった—1
⑤自分の考えがつかめた—6
⑥社会問題とのつながりを考えた—1
3 今後の自己の課題が見いだせた…0
B 授業方法に関するもの…6
1さまざまな教材や意見交流が面白かった…5
2意見文に点数がつけられてショックだった…1
進路選択についてじっくり考えるべき時期である2年生の秋を選んで、仕組んだ単元であったが、「今は、自分の将来について考える大切な時期であるが、むずかしいのであまりじっくり考えたことがなかった」者が多く、「そろそろ進路について考える機会が多くなってきて、この授業も『職業とは』ということでタイムリーだし、ためになった」「普段、社会の中でのことを考えていなかった分、深く心に残った」(以上、学習者の感想からの引用)ものの、それ以上の深まりは見られなかった。さらに、学習を経て「実感がわかなかった」とする者は6名おり、自分の問題として捉えきれなかった結果を示している。
3 1998年度実践の単元構成上の工夫
1998年度実践は、学習者に自分の問題として捉えさせきれなかった1997年度実践の反省を踏まえ、教材・学習指導の流れについて改善を加えた。特に、学習者に自分の問題として捉えさせるために「聞き書き」という学習活動を組み込んだ単元構成を構想した。
(1)教材特性とその意図
1998年度実践で教材として用意したものは次のとおりである。
教材一覧
①「一人でも生きられる、でも一緒に生きられるといいね」福島瑞穂(論説)(『福島瑞穂的弁護士生活ノート』自由国民社・1998)
・補助資料1「夫に左右される女の年金」(『実践ジェンダー・フリー教育(フェミニズムを学校に)』小川真知子・森陽子編・明石書店・1998)
・補助資料2「税金について—『100万円のカベ』の意味(妻のパート収入について)」
・補助資料3「論壇」樋口恵子(朝日新聞1993年2月10日付論壇)
②Aガードウーマン/B肩叩き屋/Cおもちゃ修理福田洋(聞き書き)(『にっぽんの仕事型録』小学館文庫・1998)
③聞き書き(生徒作品)
・補助資料「ポスト・アンダーグラウンド 前書き」村上春樹(『文芸春秋』1998・4月号)
それぞれの教材特性は次のとおりである。
教材①は弁護士である筆者が離婚の担当経験を踏まえ、両性が職業も私生活も手にしてこそ豊かといえるのではないかということを1997年の国民生活白書のデータを元にして提案したものである。文章構成として「導入」部分で「一人でも生きられる。でも一緒に生きられるといいいね」という主張を提示し、その根拠として「展開」部分で1997年の国民生活白書のデータから、女性が結婚・出産のためにいったん退職しその後パートタイム労働を選ぶのと、やめないで働き続けた場合とでは6,300万円の収入差があること、また、パートタイムの女性の年間収入分布が100万円から90万円の層に極端に集中するのは税金や年金や健康保険などの制度が「世帯単位」になっているからであることなどを具体的に示している。そのことは「男性は私生活への権利を奪われ、女性は当たり前に働いて子どもを養うための賃金を得ることが奪われている」ことにつながるというのだ。「結論」部分の、税金・年金なども個人単位になって「女性が一人でも生きられるし、男性も一人で生きられる。(そのような自立した男女であって)でも一緒に生きられるといいね」との願いを込めたメッセージに両性の関わり方が示唆される。
筆者の主張を中心にその前後の論理構成を確認し、特に「展開」部分における「データが提示される部分」「データに対する筆者の意見」「筆者の意見の根拠」を確認して、筆者の論の立て方を踏まえて筆者の主張に対する自分の意見を構築させたい。
なお、この教材で取り上げられた女性の年金制度や配偶者控除等の税金制度、健康保険制度についての解説を「補助資料」として用意した。(補助資料については、授業時間の関係で一通り目を通すぐらいの扱いとした。)
教材②は様々な仕事に就いている人に対する聞き書きのうち、三編を選んだものである。Aの「ガードウーマン」は百貨店で万引き等の摘発の仕事をする上での悩み(未成年を摘発するときのとまどいや迷い)など、あまり人に知られない仕事に就く女性の仕事への思いが読みとれる。Bは転職斡旋業という、どちらかというと人の好まない仕事に就く人の人生観・職業観が語られる。Cは定年退職後の第二の職として「おもちゃ修理」を生きがいとする人の話である。生活費を稼ぐことを考えなくてよいためか、もっぱら「生きがいとしての仕事」が語られる。A・Bと異なり、社会情勢の影響を受けないため、そのことについては触れられていない。
これらの聞き書きに対しては、何がどのような観点から語られているのか、それはわかりやすい構成となっているのかを確認したい。
教材③は学習者自身が自分の親に聞き書きしたもののうち、公開可の意思表示があったものである。高校2年生という時期の親子関係はさまざまで、親子の会話があまりない場合があることも予測したが、とかく批判的な目でしか親を見ることができない時期であることも踏まえ、聞き書きを通して親に対する見方が変化する可能性を期待した。しかし親に対する聞き書きがどうしてもできない場合も考慮に入れ、原則として親への聞き書きが望ましいが、それ以外の人でもよいとした。また、「聞き書き」対象は父・母のいずれでもよく、勤務形態(フルタイム・パートタイム)にこだわらない旨を伝えた。
書かれた「聞き書き」には2000字というかなり長めの文章を構成するための苦労の跡が感じられる。どのようなことがらについて聞くか(観点・視点)、また、どのような構成とするかという事前準備が功を奏している。
これら3つの教材の関連は、教材③の「聞き書き」活動を中心に据えて、「聞き書き」の内容把握と共に「聞き書き」の方法をつかませることも意図して教材②を置いている。「聞き書き」はどうしても個別の個々人の職業観・人生観が中心となるため、それに至るまでに、それらを包括しつつもそれより一段高いレベルからこれからの日本の家族や社会のあり方が模索できるよう教材①を配置した。
さらに、1997年度教材との相違点を整理しておきたい。
1997年度に用意した教材①は、「職業を持つことの利点」を明確に主張するものであった。筆者の主張の一つである「自分自身の人生をコントロールしているという感覚を持つことの大切さ」は明確であるだけに、それに対して自分なりの意見を形成しにくく、ただ単にこの意見に引きずられて「肯う」だけに終わってしまったのではないか、また若い女性に対して働くことの意味を考えさせることが主眼となっているため、「生活費を得る」側面が語られていないことも、理想のみに目を向けさせることにつながってしまったのではないかとも考えられる。その反省を踏まえて、1998年度の教材①には、「自立した男女が共に生きていく」ためには、どのようなあり方が望ましいのか、それには現状の何が問題なのかが就労の面から語られる教材を用意することを考えた。
1997年度教材②はデータの読み取りを通して、女性のいわゆる「M字型就労」は日本社会特有の現象であることをつかませようとしたが、現状を踏まえてどのようなあり方を希求するかという職業観の形成にはつながっていない。このことから、データが示すことがらが現状のどのような問題につながるのかという意味づけが難しかったのではないかと考えられる。それを補うために教材③を用意したつもりであったが、理想の形を追うことには寄与しても、足下を見据えての「職業観」にはつながらなかった。
その反省を踏まえ、1998年度の教材②にはまず、社会の厳しさがうかがえる仕事や人から嫌がられる仕事の聞き書きを配した。それだけでは不十分と考えて「生きがい」のみを理由に選択した仕事の聞き書きも加えた。しかし、その「生きがい」のみの仕事というのは定年後の生活費の心配をせずともよい状況下でのことであることも捉えさせようとした。その上で1998年度の教材③として自分の生活を支えてくれている人である親の仕事の聞き書きを課したものを交流させた。自分の生活の基盤がどのような仕事、どのような思いによって支えられているのかを見据えて、「職業」というものを見つめ直させたかったからである。
(2)学習指導の流れ
授業の流れは、大筋では1997年度実践と重なるが、変更点をその意図と共に記述しておきたい。
1) 学習指導目標の提示
ア 「単元のねらい」提示
単元学習に入る前に、学習者に「単元のねらい」を提示した。それは単元名だけを示すよりも単元の目的が明らかにすることができると考えたためである。学習者に提示した「単元のねらい」は次のとおりである。
単元のねらい
子どもの頃、「大きくなったら、何になりたい?」という問いに、あなたは何と答えただろうか。無邪気に自分の好きなものの名前をあげた頃もあっただろうし、もう少し大きくなると、自分が知っている狭い範囲の人物しか思い浮かばず、困った思い出もあるかもしれない。
いまのあなたは、同じ問いを前に何と答えるだろう。もしかすると、「何になりたい?」では既成の枠にとらわれてしまうから、「何をしたい?」という問いかけの方がいいのかもしれない。
自分は何をしたいかを考えることは、どのような職業に就き、どのような働き方をするのかを考えることにつながる。そういった就労の問題から、家族や社会と自分とのかかわりを考える手がかりをつかんでほしい。
イ 各教材の学習指導目標の提示
「単元のねらい」では単元の主題に対する理解を深めさせることが目的であった。それだけでは不十分であるので、各教材の学習指導目標については各教材のワークシートの設問を中心にして提示した。
教材①においては、「筆者の主張とその根拠がどのような論理構造の上に展開されているかをつかむこと」を中心課題に据えた。そのため、次のような設問を提示した。
ⅰ)「筆者の主張」は何か、それがどの段落に書かれているかを確認する
ⅱ)その「筆者の主張」を中心にして文章全体の論理構成をみる
ⅲ)教材の「展開」部分に着目し、「事例としてのデータ部分」「データに対する筆者の意見」「筆者の意見の理由(根拠)」を整理する
ⅳ)「筆者の主張内容と論の組み立てに対する意見」を書く
教材②においては、「語り手の職業観・人生観を軸として聞き書きの項目として何がどのような順で構成されているかをつかむ」ことを中心課題に据えた。そのための設問は次のとおりである。
ⅰ)A〜Cのそれぞれの職業観・人生観を整理する
ⅱ)前項の職業観・人生観を中心にして、書かれていることがらを確認する
ⅲ)A〜Cに共通することがらと、個別の事柄を整理する
ⅳ)聞き書きとして必要な項目を確認する
2)教材相互の比較
各教材の学習後に「単元のまとめ」として、それぞれの教材から読みとれたことを整理しまとめる時間をとった。それは教材全体を見通す視座を持つためである。その際、すべてのワークシートを返却し、これまでの学習を振り返らせ、「仕事を通したどのような生き方が書かれていたか」という観点で教材を比較し、まとめることを指示した。うまく整理できた数人分をプリントにし、配布して全体の場で確認した。
3)意見文の段落の柱を明示
意見文を書かせる際、段落の柱を具体的に指示した。
第一段落…単元に入る前に、テーマに関して考えていたこと(ワークシート1を参考に)
第二段落…それぞれの教材で気づいた「職業を通した生き方」の中で、取り上げたいこととその理由
第三段落…第一,第二段落のまとめとして「職業と自分」について考えたこと
これにより、一段落には一主題文という段落意識を持たせることと、学習者自身が自己の認識の変容を自覚できるようにした。
4)「聞き書き」という学習活動を成立させるための手順
ⅰ)「聞き書き」する項目の確認
教材②において、「A〜Cを読んで、三人のうち、あなたが一番興味を持つのはどの人ですか、また、それはなぜですか」「あなたが聞き書きする際の項目」というワークシートの設問を用意した。それは自分の興味関心の在処を明らかにし、それらを踏まえて、自分が聞き書きする際の項目を考えさせるためである。
ⅱ)補助資料配布
補助資料として『文芸春秋』に掲載された村上春樹の「ポスト・アンダーグラウンド 前書き」を用意した。これは、筆者が1995年の地下鉄サリン事件の加害者に聞き書きである「ポスト・アンダーグラウンド」に対して、どのような視座で臨んだかについて書かれたものである。インタビューのマナーともいうべきものにも触れられていたので、それも参考になると考えた。授業時間の関係で、流し読みのみの扱いとなったが、参考にすべき点の確認は行った。
ⅲ)「聞き書き」の事後学習
「聞き書き」としての事後指導として次の項目についてまとめ、学習の振り返りをし、ア・イをプリント一覧にして配布し、共有化を図った。
ア 「聞き書き」という体験を通して、あなたが考えたこと
イ 他の人が「聞き書き」としてまとめた文章に対する批評
ウ 「聞き書き」としてまとめた文章に対する自己批評
4 1998年度実践の成果と課題
1998年度に受け持った2学年は3クラスで、3クラスとも共通してこの単元の実践を行った。この実践の成果と課題は、5組1クラスについて見ていくこととする。
この単元は「学習者に自分の問題として捉えさせること」を課題としていたので、単元のまとめとして書いた意見文と単元終了後の「授業の評価」に見られる学習者の実態を取り上げ、その理由についての考察を行いたい。
(1)「自分にとって職業とは何を意味するか」をテーマとした意見文にみる実態
1)5組1クラス全体の傾向
①三段落構成及び「段落の柱」を指示したが、結果、三段落構成で書いた者は32名中27名であった。
②自分なりの「職業観」をつかみ、それを意見文に表現できているものをA評価としたが、それは32名中6名であった。「職業観」をつかめているものの、その根拠が弱かったり一面的であるものをA’評価としたが、それは8名であった。
③A及びA’評価以外の残り18名は、自分の考えを意見文に十分反映させることができなかった。
2)事例研究—A評価6名のうちから
優れた意見文6名分を項目ごとに整理すると次の表のようになる。(表の文言は学習者の意見文からの引用)
(表3)
<A評価6名の実態>
①単元学習前の実態
教材を学習する前に、「『職業を持つこと』について、いま、あなたが考えること」に関する考えを書かせたが、前年度と大差ない結果だった。「やりたいこと、好きな仕事に就きたい」と考えているが、「生活のために嫌なことでも我慢せざるを得ない」し、周りの大人を見ていて仕事をすることに多くの夢や希望を持てず、またさらに就職難を反映しての不安が一層募る傾向にあることがうかがえた。そのことは、表の「1 学習前に考えていたこと」を見ても、6名中4名までが「生活のため」「収入を得るため」と答えていることからうかがえる。
②教材の学習過程で気づいた「職業を通した生き方」
多くの学習者は教材②を取り上げ、仕事には生きがいや責任感、人に喜んでもらうという喜びがあることに気づいた。さらにその生きがいや誇りというものは最初からあるものではなく辛さを乗り越え、仕事を続けていく中で育まれていくものであることに気づいた人もいた。
③単元学習後の実態
職業に就くのは単に生活のためでも自分のやりたいことのためでもなく、そこにいろいろな意味を含んでいること、また自分のためだけでなく社会の一員としての位置づけが生きがいを生むこと、そういった生きがいは最初から「在る」ものでなく悩みや苦労を乗り越え仕事を続ける中で培われていくものであるといった、多面的な職業に対する見方が形成された。
<A評価のうちの1名についての実態>
A評価6名のうち1名(表3の「A」)についての、学習過程の実態を示す。
①「『職業を持つこと』について、今、あなたが考えること」(教材に入る前のテーマに関する設問)に記述された内容
自分が好きなことをやって収入があれば大変に嬉しいことだと思う。しかし、なかなかそうはいかないだろう。収入のため、生きていくためには、自分はやりたくないことでもやらなくてはいけないのではないかと考える。
②教材①一読後の「筆者の主張内容と論の組み立てに対するあなたの意見」に記述された内容
「女性の自立」ということにとても関心が持てた。今の税金・年金制度は少しおかしいと思った。働く女性の方が大変なのは目に見えているのに、一番苦しい立場に置かれるというのはおかしい。早く、個人単位になればいいと思う。
論の組立の部分はよくわからなかった。特に「データに対する筆者の意見」と「筆者の意見の理由」の違いがわからない。
③教材①学習後の「筆者の主張内容と論の組み立てに対するあなたの意見」に記述された内容
私は女だから女性の立場から見た不平等なことにはとても敏感だけど、男性の立場から見た不平等な部分にも目を向けていかなければならないと強く思った。
④教材②「三人のうち、あなたが一番興味を持つのはどの人ですか、またそれはなぜですか」に記述された内容
B「肩叩き屋」に一番興味がある。一番人の人生に関わっていて、自分のサポートの仕方が「肩を叩かれた人」の新しい人生を決めてしまうという重大な仕事である。またこんなことでお金もうけするなんてC「おもちゃ修理」の人とは大違いだと思う。
⑤教材③「あなたが聞き書きする際に、付け加えたい項目」に記述された内容
仕事内容・職業観に「毎日とても大変なのに、仕事が好きだといえるのはなぜ?」「これから仕事内容に望むこと」を付け加えたい。
⑥書いた「聞き書き」(「小学校教員」6段落構成)に見る文章構成
ⅰ)挨拶から始まる一日の仕事の始まり
ⅱ)小2の担任として感じる最近の子どもたちの情緒不安定傾向
ⅲ)子どもたちの学習面での課題(集中力の不足と個別指導の必要性)
ⅳ)子どもたちが感情をコントロールできない原因(自己解決の機会の不足)
ⅴ)職業観(無力感に襲われるときもあるが生きがいもある)
ⅵ)仕事に対する誇り
子どもの実態を描写しながらそれをどのように克服しようとしているかという仕事内容を織り込み、仕事に対する思い・誇りを述べることでまとめとしている。
(2)単元学習後の「授業の評価」にみる実態
単元学習後に授業についての評価を書かせた。その項目は以下の通りである。
ア テーマについて(興味が持てるテーマであったかどうか)
イ 学習を経て、テーマについての自分の考えが深まったか、深まったとすればどのように深まったか
ウ その原因と考えられることは何か
単元学習後の授業評価
<5組1クラス40名についての結果>(回答数38)
ア テーマについて
・興味が持てた…32
<主な理由>
・将来、絶対に考えなければならないことで、不安に思っていることだった
・今までも、今からも、職業というのは人生を決める上で重要なことだし、これからの自分の進路を決めるにあたって、職業というのがキーワードになっていくと思うので
・今、自分の進路で悩むことがあるから「職業」という言葉に敏感だった。職業と家族や世の中に関係する社会に関することがテーマとされていたので、どう関係し合うのだろうと思った
・興味が持てなかった…6
<主な理由>
・正直言ってまだ先のことだと思って興味が持てなかった。テーマが私には大きすぎたし「職業に就く」ことの意味もあまり考えたことがなかった
・この高2の2学期という時期は、みんな進路について考える時期だと思うので、良い機会だったのではないかと思う。しかし個人的にはあまり興味が持てなかった
イ 学習を経て、テーマについての自分の考えが深まったか、深まったとすればどのように深まったか
・深まった…36(うち、理由を明確に記述したもの18)
<どのように深まったか>
ⅰ)今までになかった新しい視点を得たもの…4
・現在ある職業に対する考え方の視野や将来就こうと思う職業選択の幅が広くなった
・自分の親の仕事を知ることにより職業とは一体どのようなものなのかがわかった
・今までは漠然と「仕事をする」と考えていたが、今回の単元で「その仕事は、なぜ、なんのために、誰のためにするのか」と考えるようになった
ⅱ)人間に対する理解が深まったもの…3
・今まで断片的なイメージでしかそれぞれの職業を捉えていなかったけどその人それぞれの社会観の中で誇りを持って働いているんだと思うようになった
・今までラッシュのサラリーマンは「砂の一粒」という感じで、もう毎日がただ通勤して疲れて帰って寝るだけの機械人間のようなものかと思っていたが、サラリーマンに限らずだいたいの人が自分の仕事に対して誇りや生きがいの様なものを持っているということに気づいた。そして自分は将来そういう生き方ができるだろうかと考えた
・教材①では男女の問題で税制度のことや働くという問題について考えた。教材②では仕事に対して大人に対して考えていたことと少し違うということがわかった。何よりも父に聞き書きして、父のことをいろいろ知ることができたのが良かったと思う(特に親に対する見方の変化)
ⅲ)自分なりの職業に対する考えが持てたもの…6
・仕事はやりたいことをすればいいと思っていただけだったけど、学習して「仕事を生きがいにする」ということを学んだ。そしてその生きがいは「好きな仕事に就いたからこれが生きがいになった」というのではなく、「仕事をして、違う生きがいを見つけた」という「生きがい」もあるのだと気づいた
・職業でその人の人格とか人生とかビッチリ決まってしまうわけではないが、多かれ少なかれその人の生き方や人生を色づけるものになってしまうのだということがわかった(人生における比重)
・どんな職業でも、誠意を持ってやれば生きがいにもつながるので、自分が職業に就いた時、たとえどんな職業でも、人のためを思って頑張りたいと思った。そして早く働いてみたいと思った(仕事に就くことへの展望)
ⅳ)社会との関連を見いだせたもの…5
・社会の中における仕事や自分の役割についていろいろと考えさせられた
・一人一人が気をつかうことで、社会も変えることができるし、家族との関わりも変わっていくということがわかった(概括的なもの)
・教材①で難しかったけどいろいろな制度の仕組みを自分なりに理解でき、その制度が女性にとって実は一方的に社会進出を抑圧しているものだということがわかってなんかおかしいなといろいろ考えた。教材②③では職業についてその難しさとかお金の関係、その意義など考え、教えられて、自分の中で大きなものになった(教材相互の関連について触れたもの)
・自分に合った職業を見つけるということは必ずしも自分のためだけでなく、周囲の人にもよい結果をもたらすことになるかもしれないなと思った
・働くということはそれがどんな仕事であれ誰かのためになっていて、それがたくさん集まって社会は成り立っている(社会と自己との関係に触れたもの)
・深まらなかった…2
ウ その原因と考えられることは何か
<教材名を答えたものの集計>…23
・教材①…1 ・教材②…9
・教材②と③…9 ・親への聞き書き…2
・教材①②③…2
<主な記述内容>
・大人は夢とか無いようで「生活のためだけに働いている」と思っていた。でも教材②や聞き書きをしたら、今までのは間違いだったのでは?と思うようになった。少なくとも聞き書きで話をしてくださった人たちは、生活のためというのもあるけど自分の仕事に誇りを持っていて、頑張っているんだなあと思った
・実際様々な職業に就いている人たちの人生観や職業観などを教材②③の聞き書きを通して詳しく知ることができた
・働くことは必ずしも趣味ではないしだからといって金儲けのためだけでもない。誇りを持ち働く人にとって、お金は自分の働いた結果を認められた一種の証であると思う
・教材①で仕事の社会的問題、女性の仕事の大変さを知り、教材②で全く違うジャンルの仕事についての考えを知って、最後の聞き書きで①や②にない親という身近な存在の仕事への生きがいなどを学べた。この3つの全く違う方向から職業—社会を見ることができたから
・いろいろな人の意見文やそれぞれの教材を読んで、こういう考え方もあるのかとか、この意見はあまり合わないなとか、これは自分と似ている等の感想が持て、人の意見を知るということによって認識が深まった
<A評価1名についての結果>
ア テーマについて
正直なところ、最初は全く興味がありませんでした。しかし、親に聞き書きしたことで、このテーマを少し身近に感じるようになり、興味がわいてきました。自分の身近にあるテーマの方が興味が持てる!と思いました。
イ 学習を経て、テーマについての自分の考えが深まったか、深まったとすればどのように深まったか
テーマについての自分の考えは深まったと思う。自分の就いた仕事に誇りを持っている人は、自分の中にきっちりとした人生観・職業観を持っている人たちである。また、その人たちの多くは、自分の人生観・職業観を自分の就いた仕事の中で見つけたのではないかと思うようになった。
ウ その原因と考えられることは何か
今まで自分があまりよく知らなかった職業の聞き書きをたくさん読めたこと。そしてまた、自分の身近な人の聞き書きをしたから。
(3)意見文及び授業評価に対する考察
1)5組1クラス全体に関するもの
①三段落構成及び「段落の柱」を指示したため、教材学習前と学習後の自分自身の意識の比較を意識させることができ、そういった意味でほとんどの学習者が自分なりの認識の変化を自覚することができた。
②クラス40名のうち、約1/3が根拠を踏まえて意見を述べようとしたことは、教材①での「主張と根拠の関係」の学習が一定の効果があったことを示していると考えられる。
③テーマについての興味は多くの者が持てたようである。さらに「職業と家族や世の中に関係する社会に関することがテーマとされていたので、どう関係し合うのだろうと思った」というようにテーマ設定の仕方にも関心を持たせることができた。「正直なところ、最初は全く興味がなかった。しかし親に聞き書きをしたことで、興味がわいてきた」とあるので、聞き書きを中心に据えたテーマ設定は功を奏したといえる。
④学習を経て、テーマについての自分の考えが深まったとした者がほとんどであった。どのように深まったかは、次の四つに類型化できる。
ⅰ)今までになかった新しい視点を得た
ⅱ)人間に対する理解が深まった
ⅲ)自分なりの職業に対する考えが持てた
ⅳ)社会との関連を見いだせた
前年度実践では「今まで自分が持っていなかった新しい知識を得た」とする学習者が最多(22名)であったことと比して、単に知識量が増えたというのでなく「今までになかった新しい視点を得た」などものの見方に関する深まりが得られたことは大きな成果である。さらに前年度実践では見られなかった「人間に対する理解が深まり」や「社会との関連」が8名あったことは、高く評価できる。なお、認識が深まらなかったとするものの理由としては「このテーマについてまじめに考えたのは初めてで、いろいろ考えてはみたけど難しくてまとまらなかった」というのがあった。考えをまとめることができなかったとしても、考える手だては示せたのではないかと思われる。
⑤「大人が生活のためだけに働いていると思っていたのは誤りであった」など、先入観を是正して認識を深めるために、「聞き書き」や学習者同士の意見交流、教材相互の関連比較が有効であったと学習者自身評価していることは、認識方法の意識化という点で有効であったと見ることができる。
⑥意見文におけるA及びA’評価以外の残り18名は、自分の考えを意見文に十分反映させることができなかった。教材を引き写すだけで自分の意見の代用としている、教材から得た多くの意見を未消化のままで羅列するに留まっている、自分のつかみ得たことが具体的に自分の言葉で表現されていないといった傾向をそれらの典型として捉えることができる。これをどう克服させるかが今後の課題である。
2)意見文におけるA評価6名に関するもの
①「『職業と自分』について考えたこと」において、教材を通してつかみ得たことを根拠として、職業に対する考えを自分の言葉で表現できたものが6名いたことは成果と見ることができる。
②A評価をしたものは、「自分なりの職業観をつかみ、それを表現できているもの」であったが、「意見文に見られる認識の変容過程」を見る限り、「1 学習前に考えていたこと」「2 教材の学習の過程で気づいた『職業を通した生き方』」においてはクラス全体の傾向と大差ないことが判明した。「2 教材の学習の過程で気づいた『職業を通した生き方』」において、教材②を取り上げるものがほとんどであったことは、この単元における教材①の位置づけが未消化のまま終わったと考えられる。単元学習後の授業評価で、認識の深まりが生まれたのは「3つの全く違う方向から職業—社会を見ることができたからだろう」という振り返りをした者もあったのに、その視点を意見文に生かすことができなかった。いかにして、個別の職業を通してだけでなく社会全体での位置づけを把握しつつ、自己の職業観を形成させるかが今後の課題である。
3)意見文におけるA評価のうちの1名に関するもの
①「教材に入る前のテーマに関する設問」や教材②における記述をうまく生かして認識の変容がうかがえる意見文が書けていることは評価できる。
②教材②の学習を通して、自分が聞き書きする際の項目を考えさせたことは、「聞き書き」の構成に有効であった。
③単元学習後の授業評価において、考えの深まりの原因に教材②だけでなく自分の聞き書き活動も挙げていることから、直接取り上げられていなくとも意見文に反映していることがうかがえる。また「親に聞き書きしたことでテーマに対する興味がわいてきた」と答えていることから、自分の問題として捉えさせるのに学習活動として「聞き書き」非常に有効であったと評価できる。
④教材①の学習を通して、「女性の立場から見た不平等」という社会問題だけでなく、「男性の立場から見た不平等」にも気づく視点が生み出されているのに、それは意見文に反映されていない。このことは、自分の就労のあり方と就労に関する社会問題への解決がどのように関係するのかということが未消化であったことを意味している。その関係性に気づかせ、自己の職業観に反映させる手だてが今後の課題である。
⑤自己の就労問題と社会全体での位置づけを関連させるための一つの代案を提示しておきたい。教材①では社会制度の問題点の指摘と、どのようなあり方が望ましいのかという提案(=税金・年金の個人単位制度)がなされていたが、その望ましいあり方に至る道筋が示されていなかった。ゆえに、まず「今後自分自身がどのような働き方をしていくことでこの問題に取り組むか」について意見を短文で書かせ、次に教材②③の学習後に「自分にとって職業とは何を意味するか」について同様に短文で意見を書かせ、最後に「職業を持つことが日本の家族や社会のあり方とどう関係するか」というテーマで800字の意見文に取り組ませると、今回の実践よりもっと広い視野に立った職業観の形成につながるのではないか。
おわりに
パラダイムの再構築が問題にされるようになって久しい。21世紀を目前に控えて、多くのシステムの見直しが必要とされているのである。世の中の急激な変化は当然のことながら21世紀に社会人となる学習者にも影響を与え、親世代とは異なった生き方を模索せざるを得ない状況にある。そのような中で、「自分も将来絶対職業について、仕事をしたいと思えるようになった」と、学習者が将来職業に就くことに対して、前向きに考えられるようになったことは大きな成果だった。
「子どもの頃がよかった」「学生時代に帰りたい」等、よく巷で耳にするが、私自身は「責任の伴わない自由な生活」より、「少ないながらも、責任の伴う自由が存在する現在の生活」の方がいいと考えている。それは私が私であることと密接につながっているからである。
仕事をしながらの家事・育児は正直言って辛いことも多い。しかしながら、その中でしか得られない豊かさがある。その豊かさに目を向け、困難を克服するしなやかさを育むことが授業をする際の願いであった。想いが少しでも伝わってくれればと願っている。
今春(1999年)転勤となり、8年間勤務した学校を去った。1997年度から取り組んだ主題単元によるカリキュラムの、一応の完成を見た後の異動となった。新しい学校で、また新しい枠組みでの主題単元に取り組んでいる。引き続き、残された課題解決に努めたい。
(4)高等学校国語科における主題単元の実践Ⅱ(広島大学教育学部紀要 第一部<学習開発関連領域>第49号 2000)
はじめに—本論文の位置づけ及び目的・方法
1999年度紀要論文において、1997年度紀要論文所収の単元構想から授業検証を経て1998年度に完成した単元一覧(カリキュラム)を掲げ、その特徴を説明した。
本論稿では、まずⅠにおいて、高等学校教科書「国語Ⅰ」の実態を取り上げ、その問題点を考察する。
Ⅱにおいて、「国語Ⅰ」の教科書から1ないし2教材を用いて再構成した1999年度の単元一覧(カリキュラム)を掲げる。
Ⅲでは、1999年度実践中、構造化に際して新たな試みを行った「単元 言葉をとらえる・言葉でとらえる」を取り上げ、その成果と課題を明らかにする。
さらにⅣにおいて、上記Ⅱに示した全単元(カリキュラム)を実践した結果、明らかになった成果と課題を考察する。
Ⅰ 高等学校教科書「国語Ⅰ」の実態及び問題点
現行の高等学校学習指導要領「国語」には、「国語Ⅰ」「国語Ⅱ」「現代文」「古典Ⅰ」「古典講読」「国語表現」「現代語」といった科目がある。高等学校の教科書を考察するにあたり、その中で唯一の必修科目となっている「国語Ⅰ」を取り上げることとする。
「国語Ⅰ」の教科書を見ると、全ての教科書が「現代文編」(もしくは「現代文・表現編」)「古文編」「漢文編」の三編構成となっていて、多くは三編ともジャンル別単元構成となっている。
以下に勤務校で使用している大修館書店『国語Ⅰ改訂版』(平成10年初版発行)のうちの「現代文編」についてのみ、単元名と教材名の一覧を掲げておく。
┌──────────────────────┐
│一 随想—「友情」/「紅山桜」
│二 小説(一)—「羅生門」
│ 「わたしのディッピー」
│三 評論(一)—「幸福について」
│ 「ヘンデルと力士」
│四 詩—「しろい春」「ネロ」「甃のうへ」
│ 「一つのメルヘン」
│五 言語と表現—「言葉についての新しい認識」
│ 「文章について」
│六 短歌と俳句—短歌・俳句
│七 さまざまな文章—「鉄塔を登る男」/
│ 「山猫」/「目でなく、心で見る」/
│ 「考えさせられるふたつの答え」
│八 日本語—「わたし」/「日本語らしい表現」
│九 小説(二)—「伊豆の踊り子」/「とんかつ」
│十 評論(二)—「機械と人間」/「自然と人間」
└──────────────────────┘
「現代文編」には、ジャンル単元での教科書編成からの脱却を試みたものが若干存在するとはいえ、十分とは言えない。例えば、桐原書店版『探求 国語Ⅰ』・『展開 国語Ⅰ』は、共に、随想・評論教材の単元にテーマ風単元名を付しているが、教材を見ると、教材のテーマではなく話題に関係した単元名がつけられている。以下は『探求 国語Ⅰ』における単元名と教材名の一部である。
┌────────────────────┐
│ 単元1 随想Ⅰ—宇宙と言葉—
│ 「上下・縦横・高低のない世界」
│ 「言語の開く世界」
│ 単元3 評論Ⅰ—文化の現在—
│ 「再び空知川の岸辺に」
│ 「日本のかたち・アジアのカタチ」
│ 単元5 随想Ⅱ—自己と社会—
│ 「手を見つめる」
│ 「マニアについて」
└────────────────────┘
また、角川書店版『高校生の国語1』では、3つのテーマを掲げて構成している。しかしテーマが大きすぎてどのような教材でもそのテーマに持ち込むことができ、またテーマ内はジャンル別単元となっている。
┌──────────────────────┐
│◎自分への旅立ち
│ 一 随想—「通り過ぎていく空」/「白い花」
│ 二 小説(一)—「告白〜「TUGUMI」より
│ —「羅生門」
│ 三 表現(一)「書くことの始まり」
│ 四 評論(一)「ムダこそ自分を豊穣にする」
│ 「伝え合い
│ 五 詩
└──────────────────────┘
他に「時代を見つめる」「状況の中で」という単元が設定されているが、単元内の仕組みは同様である。
教科書における単元編成については、既に内容主義に傾いているとの指摘がある1)が、その傾向は今日でも変わっていない。
「国語Ⅰ」の教科書編成の問題として、ジャンル別単元構成以外に、言語事項及び表現分野の扱い方がある。
前述の大修館書店版では「言葉と表現」というコラムを1から5まで設定し、「意味と語感」「文字を選ぶ」「文を整える」「文から文章へ」「文章の展開」という名称で、単元の間に配置している。「意味と語感」は直前の教材の中の表現を取り上げて解説している。また、「文を整える」「文から文章へ」は共に言語教材の直後のコラムであるから関連がないとも言えないが、安易である。「文字を選ぶ」「文章の展開」に至っては、前後の関連性が見いだせない。
同じく前述の角川書店版も同様である。「言葉の不思議」というコラムを1から7まで設定しているが、配置された直前の教材と関連させたものもあれば、全く関連が見いだせないものもある。
以上は「国語Ⅰ」の教科書全般に見られる共通点であるが、個々の教材を見たときには、教科書会社の基本姿勢に違いを見出すことができる。最近の作品を取り入れようとしているものと、長期にわたって採用されているものや及び他社の教科書で多く採択されている、いわゆる「安定教材」で手堅く編集したものとである。桐原書店版は前者であり、大修館書店版は後者である。
以上のことをふまえながら、「国語Ⅰ」の教科書編成の問題点として次のことを指摘しておきたい。
1 教科書の最初の単元は、これから高校生活を送ろうとする学習者を意識して「導入教材」として相応しいと思われるものを配置しているが、その後の単元の配列には系統性が見られない。
2 1単元に多くは2教材が配置されているものの、教材間の関連が見いだせない。
3 ジャンル別単元構成では逆に「例えば、『評論』とはこのようなもの」といった個々の教材の提示で、そのジャンルの定義の代わりとし、当該単元内の教材の内容を中心に扱い、改めてジャンル特性を問うことをしないため、ジャンルに対する認識が深まらないことが多い。
「指導書」(大修館書店版)を見ると、さらに次のようなことが明白になる。
1 単元内の各教材の必然性が乏しく、他の教材でも取り替えが十分可能な教材選択である。このことは、ひととおり「単元設定の理由」及び「単元の目標」、「単元の構成」が解説されてはいても、その内容は一般論的なもので、実際には単元として機能していないことを示すものである。
2 1999年度からは、そういった不十分な「単元設定の理由」及び「単元の目標」、「単元の構成」さえも記述されていないものが出てきており、1教材ごと、1時間ごとの指導案に代わってきている。これは学校現場の声を反映した結果であるとも考えられるので、一概に教科書会社のみを責めるわけにもいかないが、「即授業展開に役立つもの」を求める風潮には危機感を覚える。「単元とは何か」という認識を持ち、授業者ひとりひとりが自分で授業を創る必要性を強く感じる。
なお、『月刊国語教育』2)で「新時代の教科書を創る」と題した特集が組まれており、教科書が学習材として機能するための要件が考察されてはいたが、現行教科書に対する具体的な批判や提案はなかった。高等学校の教科書編成に対する考察が少なすぎることが、教科書改善がなかなか進まない要因ともなっていることを指摘しておきたい。
Ⅱ 1999年度 国語Ⅰ(現代文)における主題単元一覧
既述の勤務校での使用教科書(大修館書店版)での「国語Ⅰ(現代文分野)」の年間学習指導計画として、「友情」「とんかつ」「考えさせられるふたつの答え」「羅生門」「言葉についての新しい認識」という教材をこの順で共通して扱うことになった。したがって、これらの教材を取り入れた単元を創ることにした。
既に1997年度紀要論文においてカリキュラム編成原理を五点提示し、単元を配置する順についても言及しているが、1999年度は共通教材という制約がある中での実践であったので、単元配置は、共通教材を扱う順序に依らざるを得なかった。
また、「共通教材」は、それぞれ次のような問題を抱えていたので、それを克服するための単元を創った。
・「友情」…自分とは異なる他者との出会いのみが自己発見につながるとする点で一面的
・「とんかつ」…困難に耐えるという正統派的な成長しか描かれていない点と、成長過程が描かれていない点で一面的
・「考えさせられるふたつの答え」…問題提示はあるが、文明社会に生きる者としてどういう解決法があるのかが提示されていない
・「羅生門」…場面設定と下人の心理の変化のつながりに工夫があり、物語としての面白さは否定できないが、安易に「人間の本質は悪である」もしくは「限界状況下では仕方がない」といった人間観に結びつくおそれがある。
・「言葉についての新しい認識」…言葉に対する「新しい認識」として展開されるべきはずのことがらが、事例を示した後の「何かである」といった曖昧な指摘でしかなく、しかも論の立て方が平板で深まりがない。
1999年度のカリキュラム編成原理について以下に掲げておきたい。
<カリキュラム編成原理>
① 年間カリキュラムを全て主題単元で構成する。
② 学習者が学ぶべき認識の対象領域を、「自己」「言葉」「社会」「自然・文化・科学」「人間(生き方)」の5領域になるべく沿わせる。
③ 1年間で扱う主題単元数は合計5つとする。
④ 1単元に教材を3つ用意する。
⑤ 各単元で育成する言語能力の明確な位置づけをする。
これにしたがって創造した単元一覧(カリキュラム)は論文末尾の「表1」のとおりである。
Ⅲ 1999年度実践「単元 言葉をとらえる・言葉でとらえる」
1999年度実践中、単元構造として新たな試みを行った「単元 言葉をとらえる・言葉でとらえる」を取り上げる。
1 単元設定の趣旨及び教材一覧
「単元 言葉をとらえる・言葉でとらえる」の認識対象領域は「言葉」である。以下に、単元設定の趣旨及び教材一覧を掲げておきたい。
単元設定の趣旨
人間と他の動物との違いは、ひとつに「言葉」を使用するかしないかにあるという。しかし、普段私たちは言葉について意識を払っているとは言い難い。この単元では、言葉は、表現・伝達の手段である以前に、物事を認識する手段であり方法であることを、言葉でとらえ、言葉と、それを用いる人間の関係を考えたい。
教材一覧
①「anonymⅠ」(詩)谷川俊太郎(『空の青さを見つめていると』角川文庫)
②「言葉についての新しい認識」(論説)池上嘉彦・教科書教材
③「わたし」(論説)森本哲郎・教科書教材
2 単元構成上の工夫
(1)「言葉についての新しい認識」の教材特性
「共通教材」である「言葉についての新しい認識」の文章特性を、まず明らかにしたい。
「言葉についての新しい認識」という文章は、教科書本文に脚注が付せられ、筆者の略歴紹介と共に「『ことばの詩学』(1982年刊)をもとに、本教科書のために新たに書き下ろされたもの」という解説がなされているので、ひとつながりの完結した文章として扱う。
この文章は形式的に一行あけの三段構成となっているので、それに従い文章構成を以下に示す。(①〜⑰は形式段落番号を表す)各段落の要点は省略する。
Ⅰ 言葉の意味内容は一定でなく、また文化による影響が大きい
①話題提示/②事例提示/③言葉の特性1(比喩を用いての説明)/④言葉の特性2(例示しての説明)
Ⅱ 言語は思想を表現し伝達する以上のものである
⑤話題提示/⑥言語の定義/⑦問題提示/⑧問題解明1/⑨問題解明2/⑩話題まとめ
Ⅲ 言語は文化を象徴し、言語が違えば、ものの見方も違ってくる
⑪言語についての新しい認識1(例示しての説明)
⑫補足説明1/⑬補足説明2/⑭言語についての新しい認識2/⑮事例提示/⑯補足説明1/⑰補足説明2(例示しての説明)
「言語は表現・伝達の手段である以前に認識の手段であり方法であるから、言語が違えばものの見方も違ってくるし、個人によっても異なってくる」という主旨であればわかりやすいのに、この文章はこのようにすっきりとまとめきれるものになっていない。
その原因の第一は、「現在における言語への関心は、こういった問題よりももっと深いところにある何かと関わっているように思える」(⑤段落)「言語というものは『手段』以上の何かである」(⑩段落)「このようにとらえられた言語は、単なる表現、伝達の手段以上の何かであることは確かである。」(⑰段落)という記述に見られるように、問題提起だけでなくまとめの段落においても、明確に説明されるべきことがらが、「何か」という曖昧な表現で済まされていることにある。
第二として、第一段から第三段の展開が論理的でないことがあげられる。第一段で触れられる「文化」の問題は、「方言」が例示されていることからわかるように、同一言語を使用する上の問題である。第二段で「言語は思想を表現し伝達する手段以上の何かである」という問題に移った後、第三段で再び文化の問題に戻るが、この場合の「文化」とは異言語を使用する上の問題である。このように、異なることがらがその問題の比重も明らかにされないまま並べられており、論に深まりは見られない。
第三として、異なる言語による認識の枠組みの違いという問題と、個々人の使い手としての力量による問題とが整理されないまま、言語に関することがらを羅列していることがあげられる。第一段の言葉とその意味内容との関係は、ソシュールの言語学用語でいう、シニファン(=「能記」と訳され、言語記号の音声面)シニフィエ(=「所記」と訳され、言語記号の意味内容)の関係について触れた部分であると思われるが、この両者の関係について取り上げるならば、どの言語にも共通する、使い手の力量の問題につながっていることにまで言及する必要があるのではないだろうか。
第四として、論の歯切れの悪さがあげられる。第三段の⑪段落で「言語は文化を象徴する」といっておきながら、⑫段落で「言語に現れている区別がすべて何らかの文化的事情と結びつくとは限らない」と譲歩してみせ、また更に⑬段落で「しかし、言葉の上で区別があるかどうかということで、物事のどの点に注目し、どの点に注目しないで済ませるかが違ってくる」と転じるなど、筆者の真意がよくわからない。さらに最終段落の「これが現代における言語についての認識を支えている一つの柱である。」も明確さを欠いている。
第五は事例の不適切な用い方である。第一段の④段落において、「一つ一つの語には個性があり、それは長い間にわたって文化の中で培われてきたもので、そのような語には特別の愛着を感じる」とする事例に「方言」のみを提示するのは、余りにも偏りがあると言わざるを得ない。
以上のことから、この文章は論説教材として、ことば選び、論の展開、論旨いずれの面からも問題を抱えた教材であると判断せざるを得ない。
(2)単元の構成と意図
教材「言葉についての新しい認識」はこのような問題を抱えているが、これを用いて言葉の単元を組む必要に迫られ、二つの面から単元構成を考えた。
一つは、「異なる言語による認識の枠組みの違い」について、別の角度から切り込んだ教材を用意することである。「言語についての新しい認識」本文で、具体的な対象を表す語の事例をあげて説明してはいるが、⑯段落に「しかし、具体的な対象を表す語ばかりでなく、もっと抽象的な概念を表す語にも、そしてまた語法、文法の面にも、同じように違いがあって同じような作用をしているかもしれないということを考えてみるならば、言語というものの影響力は、もっともっと根本的なところで働いているのかもしれない。言語は人間の表現、伝達の手段であるどころか、むしろ知らないうちに人間を支配している君主であるかもしれないのである。」とあるだけで、それ以上は触れられていない。ゆえにもっと意識の面に影響する事例を扱っているものとして、同じ大修館書店の教科書で別の単元として組まれていた教材「わたし」を取り上げることにした。
教材「わたし」は、日本語の一人称の多様性が日本人の自我意識の高さの現れではなく、対人関係を気にする意識の現れであることを、論じたものである。
導入として、ヘビは二百以上、ライオンは五百以上、タカは千以上の同義語があるアラビア語を事例としてあげ、同じ対象にいくつもの言葉があるということは、それだけその対象についての関心の度合いが高いという解釈をまず示している。それに手がかりに、日本語の一人称の多さは日本人の自我意識の現れかという問題を提示し、そうではないということを、欧米人と比較した日本人の自己意識の質的違いを風土の違いという点から展開していくのである。
最終段落は「じっさい、日本人である私自身、相手によって『わたし』というべきか、『ぼく』というべきか、『おれ』といってもいいか、それこそ無意識のうちに心を配っているのである」という文で終わり、自身の意識の振り返りはあっても、問題意識はない。つまり、この文章は、日本人の自我意識の解明はなされていても、そのことの何が日本社会において問題かという切り込み口がないという問題を抱えている。しかし、教材「言葉についての新しい認識」に比べて論理展開が平板でないことを評価し、また、教科書の多くの論説教材がこの文章と同じ問題を抱えていることを指摘するために、教材として扱うことにした。
もう一つは、人間と言葉との関係に真摯に切り込むことのできる教材を用意することである。教材「言葉についての新しい認識」では、学習者に言葉の使い手としての自己の在り方に迫りきれない。教材「わたし」も同様である。そこで、谷川俊太郎の「anonymⅠ」という詩を取り上げた。以下に作品を掲げる。
┌──────────────────────┐
│黙っているのなら/黙っていると言わねばならない
│書けないのなら/書けないと書かねばならない
│
│そこにしか精神はない/たとえどんなに疲れていよ
│うと/一本の樹によらず 一羽の鳥によらず/一語
│によって私は人
│
│君に答えて貰おうとは思わない/君はただ椅子に凭
│れ/君はただ衆を恃め
│
│けれど私は答えるだろう/いま雑木林に消えてゆく
│光に/聞き得ぬ悲鳴 その静けさに
│ (『旅』1970年刊より)
└──────────────────────┘
学習者を、言葉によって自分を自分で在らしめようとする厳しさに向き合わせたいと考えた。それは具体的にはこの詩の「一語によって私は人」をどのように解釈するかを問うことである。学習者の実態として、言葉に対する認識が余り深くないことが予想されたので、あえて、教材①として、まずこの詩に出会わせ、学習者の意識に揺さぶりをかけ、教材②、教材③を経て、再び教材①に戻り、「教材②・教材③を学習し終えて、この詩における『言葉のはたらき』について考えること」を問うことにした。
(3)学習指導の流れ
この単元の学習指導の流れは次のとおりである。
<学習指導の流れ>
第1次 ・「単元のねらい」及び「学習目標」提示
・単元に入る前のテーマに関する設問
第2次 教材①
第3次 教材②
第4次 教材③
第5次 教材①
第6次 ・単元のまとめ1—教材ごとのまとめ
・単元のまとめ2—「単元全体のまとめの文章」を書く
第7次 授業の振り返り(授業についての感想)
第1次に学習者に提示した「単元のねらい」及び「学習目標」、「単元に入る前のテーマに関する設問」は次のとおりである。
<単元のねらい>
人間と他の動物との違いは、ひとつに「言葉」の使用の有無にあるという。確かに毎日、私たちは言葉を使って生活している。しかし今までに、人から発せられた言葉や自分の使っている言葉について、特に意識したことはあるだろうか。あるとしたらそれはどんな時だっただろう。
この単元では、言葉のはたらきをとらえ直し、言葉と、それを用いる人間との関係を考えてみよう。
<この単元における学習目標>
① 3つの教材について、それぞれ、どのような言葉のはたらきが提示されているかをつかむ。
② 3つの教材で提示された問題の、関連性を把握する。
③ 「人間と言葉との関係」について自分自身の考えをまとめる。
<教材に入る前の、テーマに関する設問>
・「言葉」はどんなはたらきをしていると、あなたは考えますか
各教材すべて、「一読後の感想」を書かせ、その都度口頭発表による意見交流を行った。
教材②及び教材③については、初読の「疑問点」を書かせた。出された疑問点は、各クラスごとに「疑問点一覧」として項目別に分類し、形式段落順に整理して、プリントにして配布した。項目として「(読み違えがあり)書かれていることがらを確認する必要のあるもの」「ことがらの具体的内容を問うもの」「ことがらの評価を含むもの」に3分類した。
その「疑問点一覧」を用いて、そこから関連する疑問点をまとめて、その教材を読み深めるための学習課題として、いくつかに絞り込んだ。
その「学習課題」を5〜6名でグループ討論させ、各グループごとの発表を通して問題解決を図った。
また、第2次から第5次では、各教材の学習指導目標を各教材のワークシートの設問を中心にして提示した。教材②及び③は論説教材であるので、文章の論理構造を問題にし、論旨や文章構成にかかわる設問を用意した。その後、教材の文章特性(論の展開の仕方、用語の用い方、表現の工夫など)を確認した。
さらに各教材の学習後に「この作品から『言葉のはたらき』について考えたこと」を書かせ、口頭発表による意見交流を行った。
単元のまとめとしてまず、各教材ごとに「言葉のはたらき」について考えたことを整理させ、その後、「自分を振り返りながら、『言葉と、それを用いる人間の関係』という観点から今後の生き方について考えたことを、ひとまとまりの文章に書く」ことを指示した。その際、3段落構成の柱を指示した。(第1段落—単元学習に入る前に、テーマに関して考えていたこと/第2段落—それぞれの教材の学習でつかんだことのうち、取り上げたい「言葉のはたらき」とその理由/第3段落—1、2をふまえて、今後の生き方について考えたこと)
優れたものをプリントにして配布し、まとめとした。
3 成果と課題
本単元の実践は3クラス120名を対象に行ったものであるが、1組1クラス40名を対象に、教材の学習の前後における言葉に対する認識を比較する。併せて単元学習後の「授業に対する評価」を分析し、成果と課題を明らかにしたい。
(1) 「『言葉』はどんなはたらきをしていると、あなたは考えますか」という教材に入る前の、テーマに関する設問に見られる学習者の言葉に対する認識(回答数40であるが、複数回答あり)
『国語教育研究大辞典』3)の「言語機能」の項に、ヤコブソン説に岩淵悦太郎説を組み合わせた分類表があり、それによると「他に対する機能」として、社交・伝達・指令の3機能、「自分の中での機能」として、認識・思考・発想・自己表出の4機能、「言語自体の機能」として、注釈・保存の2機能の、計9機能があげられている。今回、学習者の認識を分類するにあたり、他者との双方向の意志疎通という意味で「伝達」の代わりに「コミュニケーション機能」を項目として立て、単に自分の気持ちを吐露して感情の整理を行う「表出」とは区別した「自己表現機能」を加えたい。これらの項目で分類した結果は以下のとおりである。
① 社交機能……………………3
② コミュニケーション機能…38
(概念の説明手段…1を含む)
③ 指令機能………0 /④ 認識機能………1
⑤ 思考機能………0 /⑥ 発想機能………0
⑦ 自己表出機能…5 /⑧ 自己表現機能…2
⑨ 注釈機能………0 /⑩ 保存機能………0
これを見ると、学習者の大半が言語の「コミュニケーション機能」に目を向けていることがわかる。
(2)単元まとめの文章に見られる言葉に対する認識の深まり
このクラスで、認識の深まが見られる4名の文章を取り上げる。「単元まとめの文章」から抜き出す形で、認識の変容過程を整理する。(以下、数字は三段落構成の段落順を示し、段落の柱は前述したとおりである)
A 1 言葉とは単に人と人がコミュニケーションを取ることと考えていた。
2 教材③により、教材②での「言葉は単なる伝達手段以上の何か」という意味がわかってきた。言葉は、生活や文化、考え方・生き方、そういったその人の在り方というのものを反映しているのではないかと考えることができた。こう考えると教材①の意味が分かってきて、言葉とは自分という一人の人間を確立するためのものだと考えることができた。これらから言葉は私たち自身を表していると考えられると思った。
3 自分たちの言葉である日本語を誇りに思い、他国の言葉も注意を払ってその考え方を理解しあっていきたい。
B1 言葉とは自分と他人の意志を理解し合うはたらきがあるということしか考えられなかった。
2 教材①から、言葉とは他人と違う自分というものをつかむためのものだということが分かった。作者は、どんな時でも自分は自分でありたいと言っているような気がした。その自分が自分であるためには、言葉を使い、自分の本当の意志を伝えることで、他人と違う今まで気づかなかった自分や、自分の存在を見つけることができるんだと思った。初めは「聞き得ぬ悲鳴 その静けさに」は、他人の意志を自分が聞いてあげることだと思っていたけど、学習を終えて、それは自分の意志を自分が聞くということかなあと思った。
3 自分というものを言葉で表現し、他人に伝えることが大切だと思う。今は国際化も進み、世界の中でも自分たちの意見を伝えていかなくては何が起こるか分からないんだから、言葉をしっかり使いたいと思う。
C1 言葉とは自分の意志を伝えることのできる伝達手段だと考えていた。
2 教材③で、今まで気づかなかったことを発見した。それは逆に言葉によって「自己」を表現できないでいるというものだった。
3 日本人にとって言葉は、使い分けることによって人間関係や世間とのつながりをひらくのにいいものだとは思うけど、その反面、言葉によって支配されてしまっているもう一人の自分がいることに気がついていかないといけないと思った。そして、自分にとって言葉とは何なのかを、自己を表現していくためにも理解していかないといけないと思う。
D1 言葉とは人と人をつなぐ重要な役割をしていると思ったけど、これは自分の意志を相手に伝える、単なる伝達手段としてしかないと思っていることと同じだった。
2 一番印象に残ったのは教材①である。初めは全く意味が分からず、このテーマとどう関係しているのかも分からなかったが、教材②・③を学習して教材①に戻ると、関連が見えてきた。自分というのはかけがえのない存在であり、独立した一個の人格だから、自分で自分を見つめ、気づかなかった自分を見つけていくものだと思った。そのためには「言葉」というものが必要になる。言葉は単なる伝達手段でなく言葉にすることによって自分を発見できるものなんだと分かった。
3 言葉は人間が暮らしていく上でとても重要だと分かったので、言葉を大切にしたい、自分の意見を持ちたいと思った。
「言葉とは自分という一人の人間を確立するためのもの」「言葉は私たち自身を表している」「自分が自分であるためには、言葉を使い、自分の本当の意志を伝えることで、他人と違う今まで気づかなかった自分や、自分の存在を見つけることができる」「言葉にすることによって自分を発見できるもの」という記述から、ものの認識や自己認識の手段であり方法でもあることに気づくことができたと評価できる。
さらには「逆に言葉によって『自己』を表現できないでいる」という記述に見られる、言葉に対する無自覚によって引き起こされる自己表現の阻害(人間疎外)の発見は、大きな認識の深まりである。
(3)単元学習後の「授業に対する評価」
単元学習後、「授業に対する評価」として次の3点についての記述を求めた。(回答数39)
┌──────────────────────┐
│1 興味が持てるテーマであったかどうか
│2 学習を経て、テーマについての自分の考えが
│ 深まったか、深まったとすればどのように深
│ まったか
│3 2の原因と考えられることは何か
└──────────────────────┘
それを分類すると以下のような結果となった。
1 テーマについて
・非常に興味が持てた…3/・興味が持てた…27/・次第に興味が持てた…5/・余り興味が持てなかった…2/・興味が持てなかった…1/・難しかった…1
2 学習後の、自分の考えの深まり
・深まった……39/・深まらなかった……0
☆どのように深まったか(複数回答あり)
・言葉への関心が深まった…6
・言葉の働きについて新たな知識を得た…12
・自分なりの考えがつかめた…2
・「言葉のはたらき」に関する認識(教材②・③での提示)が深まった…10
・自己発見・自己表現・自己確立に重要なものという認識を得た…9
3 その原因と考えられること(複数回答あり)
教材に関するもの—15
・教材①による…2/・教材②による…1
・教材③による…5/・教材全て…3
・教材②・③による(言葉が人間の思考様式に深く関係していることを知ったから)…2
・教材の事例が手がかりとなった…2
学習方法に関するもの—23
・教材ごとに文章構成を確認したこと…6
・違う角度からの人の意見を聞いていくうちに自分の中で新たな考えが生まれ理解も深まった。…9
・教材に入る前にそれまでの自分の考えを書き留めておくことは、教材を学び終えた後、どのように考えが変わったか、どんなことを知ることができたかがはっきり分かるので、良い学習方法だと思った。…1
・複数の教材を読み比べることで、一つの教材で分かりづらいことが他の教材から分かることができたのも良かった。…1
・3つの教材の観点の違いや共通点を、文章構成を見ることで、さらにわかりやすく考えることができた。…1
・教材①が全然分からなかったけど、教材②・③の学習後に教材①に戻ったとき、沢山のことが見えて来たので、初めに教材①を読んで疑問を持っておいたことが良かったと思う。…2
・教材③の、事例後の説明箇所で、教材②で分からなかったことが分かるようになったから…1
・単元ごとに「まとめ」があるので「まとめる力」も学習できるのはよかった。…1
・他の人の単元まとめの文章を読んだこと…1
学習内容に関するもの—2
・学習を通して、改めて「自分」というものについて考えさせられたから…1
・このテーマで教材を考えることが楽しくなってきたから…1
単元学習後には35名の学習者がこの単元に「興味が持てた」、そして回答者全員が「学習後、自分の考えが深まった」と答えている。
「どのように自分の考えが深まったか」についても、関心の深まり、新たな知識の取得、教材内容に即しての認識の深まり以外に、「自己発見・自己表現・自己確立に重要なものという認識を得た」とする者が9名に上ることは、学習者が言葉の使い手のしての自己の在り方に迫ることができたという意味で評価できる。
考えが深まった原因として、「意見交流」が最も多くあげられ、次いで「文章構成の確認」があげられた。これらは各教材の内容把握だけでなく、教材相互の比較にも有効だったということを示している。
なお、複数教材を読み比べることの効果について取り上げられたものもいくつか見られた。単元学習が機能していることの表れと見てよいであろう。
以上は、この単元の成果であるが、「自分の考えが深まった」と答えていても、やはり、関心の深まり、新たな知識の取得、教材内容に即しての認識の深まりの留まっていることが課題である。「関心の深まり」に分類したものは「言葉の一つ一つの意味を考えるようになった」「言葉自体に目を向けて見ようと思うようになった」等であり、「新たな知識の取得」「教材内容に即しての認識の深まり」同様、具体性に乏しく、自分の言葉による表現が見られない。
「単元まとめの文章」においても同様である。認識の深まりが自分の言葉で表現できているものが少なかった。表現力は認識力に裏打ちされたものであるから、即効的な解決策は見あたらないが、一案として単元全体をまとめる文章を書く前に、まず文章の主旨となる「言葉とそれを用いる人間の関係についての自分の新しい認識」を自分の言葉でまとめることを課してもよかったのではないか、と今考えている。
Ⅳ 教科書教材を取り入れた主題単元による年間カリキュラムの成果と課題
教科書教材を取り入れた単元による年間カリキュラムは、論文末に「表1」として既に提示したとおりである。このカリキュラムによる実践の後、年度末に「1年間の授業を終えてのアンケート」を実施した。
五つの単元名と教材一覧を列挙し、3クラスともに「印象に残った単元とその理由」「興味の持てなかった単元とその理由」「1年間の授業で得たこと・得られなかったこと」「授業担当者への手紙」という4項目で書いてもらった。「印象に残った単元」及び「興味の持てなかった単元」の統計は次のとおりである。(回答数は1組36、6組40、9組35の計111)
☆印象に残った単元 / ☆ 興味の持てなかった単元
│ 組│1│6│9│計│ 組│1│6│9│計│
│1自己│3│3│0│6│自己│5│6│4│15│
│2自己│12│14│10│36│自己│6│0│4│10│
│3社会│6│5│5│16│社会│6│9│2│17│
│4人間│14│11│18│43│人間│5│6│3│14│
│5言葉│13│9│3│25│言葉│5│16│17│28│
「1年間の授業で得たこと」として以下のような回答を得た。なお、記述なしは6名だった。「考える力を得ることができた」「今までより、考えて自分の意見が言えるようになった」「1年間で自分の中の考えがどんどん深まっている気がする。自分の中の奥の方にあったことが引き出されているような感じ」「固定した考えからものごとをいろいろな角度から見ていくというように視野が広がった」「クラスのみんなとの意見交流によって、今まで自分の見方だけで見ていたものがいろいろな視点から見やすくなった」「人間が生きていく上で必要なことを学習してきた」「自分はどんな人間なのかを知り、それをふまえてこれからの他人とのつきあい、生き方を学んだような気がした」
「1年間の授業で得られなかったこと」に対する記述は「なかった」との回答がほとんどの中、わずかに「考えや思いを文にしてそれをつなげ、ひとまとまりの文章にする力」「発表の時、いい意見や発言ができなかったこと」「教材を1回読んで作者のいいたいことなどがすぐに理解できなかったこと」「文章構成の上手な方法」という回答があった。
以上のことから、総体として、学習者にとって得ることの多いカリキュラムであったと評価できる。
回答の中には、1年間の学習の過程のうかがえるものがいくつかあった。その一例をあげておきたい。
☆1年間の授業で得たこと・得られなかったこと
中学校の時と違い、自分で考え、自分の答えを出さなければならなかったので、、自分についてやいろいろな事についてじっくり考えるようになった。今まで一つのことを自分の考え方でしか考えられなくて視野がすごく狭かったけど、いろんな人の意見を聞く中で驚いたり納得したりして、いろいろな角度から自分も考えられるようになった。教材を学習していく中で、この世の中が今どういう世の中か見えてきて、いかに自分が何も考えず大きな流れの中に流されていたか気づいた。今まで自分を知るといっても人と比べての自分で、内面的に自分というものを見てきていなかったので、孤独になったりしてこれから生きていく中で自分とどう向き合うか考えるようになった。全ての単元を学ぶうちに「生きる」ことについてすごく考えるようになった。
☆授業担当者への手紙
どの単元もテーマが学びたかったことだから、いつも次はどういう教材をするんだろうとワクワクしていました。いろいろな教材を学び、どう考えたかを書く時に、考えが発展しなかった時とかは苦しくて、国語でこんなに自分と向き合ったのは初めてでした。いろいろな教材を学習すると、いつも今の自分はどうなのかと考え、このままいったらこの世の中の危ない部分など気づかずに、時間に追いまくられ、快適さを追い求め、人の意見を自分の意見と思う没個性的な人間になっていたんじゃないかと思います。そして単元を学習する途中で、「人間が生きるとは一体どういうことなのか」ということを考えるようになって、1個の人間が存在するだけで多くの犠牲を伴うということ、苦しくても苦しくてもそれでも生きていかなければいけないこと、その上でどう生きるのか、何のために生きるのか…と今ずっと考えています。国語を勉強する中で、心の成長が少しはあったんじゃないかと思います。1年間いろいろな教材を使っての授業、すごく楽しかったです。ありがとうございました。
決められた教科書教材を取り入れ、さらに単元配置においても制約がある中での実践であったが、この主題単元カリキュラムは、「主体の育成」すなわち「自立のためのプログラム」4)として機能したと評価できる。
課題としては、第一に、テーマ設定の問題があげられる。同一の認識対象領域「自己」が二つ続き、「自然」「文化」「科学」に関するものがなかった。1年間に取り扱うことのできる認識対象領域は限られているので、できれば重なりがない方が望ましい。
第二に、単元配置の問題である。今回の単元の順序は「共通教材」の順に依ったが、「とんかつ」「羅生門」については、「羅生門」より「とんかつ」の方が平易な教材であると判断して、それを先に持ってくることを提案し、同僚の同意を得た。教科書に編成されている順が必ずしも適切であると言えないことをふまえ、教材を扱う順序が、適切かどうかの十分な検討が必要である。
第三に、「共通教材」を決定する際の、教材としての質の問題である。現場の実態として、年度始めに用いる教科書の教材全てに対し、教材としての質の検討を行うのは時間的に非常に困難である。しかし、それなしには、例えば「言葉についての新しい認識」のような問題を多く含む教材に、学習者自身が苦しめられることになる。学習直後ではなく最終的な「一年間の授業を終えてのアンケート」で「単元 言葉をとらえる・言葉でとらえる」が賛否分かれる結果となったのは、この教材のわかりにくさによるものであることが、アンケート結果から判明している。
おわりに
1999年度の実践を振り返ってみて、テーマ選択、教材選択における不自由さはあったが、学校現場の状況からいうと、何の制約もない単元創造より現実的な提案となるのではないかと考えている。今年(2000年)度、引き続き、同様な制約がある中での、2年次3年次のカリキュラムを創っている。考えること、意見交流することの楽しみを感じてくれる学習者の反応を励みに、私自身楽しみながら実践を続けていきたい。
【注】
1)森田信義・種谷克彦、「高等学校国語科における論説文指導の研究Ⅰ」、広島大学学校教育学部紀要、第Ⅰ部、第19巻、1997年、p.19
2)東京法令出版、1997年2月号
3)国語教育研究書編・明治図書・1988年刊、pp255〜257
4)森田信義・葛原昌子、「高等学校国語科における主題単元の構想」、広島大学学校教育学部紀要、第Ⅰ部、第20巻、1998年、p.3に高等学校国語科の学習指導目標私案を出している
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休