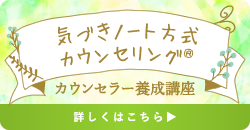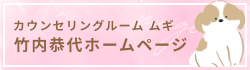- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 長田弘の詩
- 「なぜ?」という疑問を発しなくなる〜長田弘の詩「あのときかもしれない 六」〜
「なぜ?」という疑問を発しなくなる〜長田弘の詩「あのときかもしれない 六」〜
2018/04/13
「あのときかもしれない 六」 長田 弘
「なぜ」とかんがえることは、子どものきみにはふしぎなことだった。あたりまえにおもえていたことが、「なぜ」とかんがえだすと、たちまちあたりまえのことじゃなくなってしまうからだ。
たとえば、釦だ。きみの服の釦は右がわに付いていて、釦穴は左に付いている。左合わせだ。それはきみが男の子だからだ。女の子の釦は左がわに付いていて、釦穴は右がわに付いている。右合わせだ。どの男の子の、どの女の子の釦もそうだ。あたりまえのことだ。でも、どうして男の子は左合わせで、女の子は右合わせでなきゃいけないんだろう。なぜだ。そんな区別なんてしなくったって、男の子は女の子じゃないし、女の子は男の子じゃないのだ。
あるいは、本だ。きみは一冊の本をもっていた。きみの友人もおなじ本をもっていた。おなじ本だけれど、きみの本はきみのもので、友人の本は友人のもので、二冊の本はべつの本だった。友人の本はきれいだったが、きみの本はすこし汚れていた。だけど、ちがう二冊の本は、やっぱりおなじ一冊の本だった。きみの本で読んだって、友人の本を借りて読んだって、おなじ本を読んだことに変わりはない。二冊の本はおなじ本だった。なぜだ。ちがう本だったというのに。
あるいは、鏡だ。鏡のまえに立って、子どものきみは右手をあげる。すると鏡のなかのきにが、左手をあげる。きみが左の耳をひっぱると、鏡のなかのきみは、右の耳をひっぱった。なぜだ。鏡だからだ。鏡のなかでは、右と左はかならず逆になるからだ。あたりまえのことだ。椅子をきみの左がわにおく。すると鏡のなかの椅子は、きみの右がわにある。
しかし、ときみは疑ったのだ。そして、ごろりと鏡のまえに寝ころんだ。寝ころんだきみの頭は右、きみの足は左。だが、へんだ。鏡のなかのきみの頭も右、きみの足も左。つまり、おなじだ。あ、右と左が逆にならない。なぜだ。おなじ鏡なのに。
そういう「なぜ」がいっぱい、きみの周囲にはあった。「なぜ」には、こたえのないことがしょっちゅうだった。そんな「なぜ」をかんがえるなんて、くだらないことだったんだろうか。誰もが言った、「かんがえたって無駄さ。そうなってるんだ」。実際そうかんがえるほうが、ずっとらくだった。何もかんがえなくてもすむからだ。しかし、「そうなってる」だけだったら、きみのまわりにはただのあたりまえしかのこらなくなる。そしたら、きみはものすごく退屈しただろうな。「なぜ」とかんがえるほうが、きみには、はるかに謎とスリルがいっぱいだったからだ。けれど、ふと気がつくと、いつしかもう、あまり「なぜ」という言葉を口にしなくなっている。
そのときだったんだ。そのとき、きみはもう、一人の子どもじゃなくて、一人のおとなになってたんだ。「なぜ」と元気にかんがえるかわりに、「そうなっているんだ」という退屈なこたえで、どんな疑問もあっさり打ち消してしまうようになったとき。
(『深呼吸の必要』晶文社刊)-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休