沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

至福の大宇陀時間
2022/04/30
さらにひとつ大きくなって。(歳をとって、というのをやめにした。…「ひとつ大きくなった」のよ。)
その名も「正午の会」。12時始まり。
安曇野の「森のおうち」からの手紙
2022/04/23
長谷寺の切り絵御朱印
2022/04/22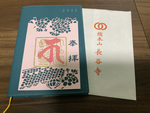
この日も、やっぱり忘れていて。
あーあ。…まあ、直に書いて貰うのではなく、後で紙に書かれた御朱印を貼り付けてもいいのだけれど、ね。
でも、なんとなく「貼り付け」は味気ないなあと思っていたら。
なんと。「切り絵」の御朱印がある、というではありませんか!私のフォーカシング・レッスン Act2〜私を取り戻す〜筒井優介さんとのフォーカシング(2)〜
2022/04/21
私のフォーカシング・レッスン(4)〜セラピーの関係様式としてのフォーカシング〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈7〉
2022/04/19
池見陽先生の「Asian Focusing Methods」セミナーの続きです。
午後の部に行く前の、私の中で想起されたあれこれを、もう少し。
里子に出された「さら」のその後
2022/04/15
私のフォーカシング・レッスン(4)〜フォーカシングのもうひとつの軸はスペースを取ること〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈6〉
2022/04/14
私の書の時間(1)〜筆先の向きを意識する〜
2022/04/13
私のフォーカシング・レッスン(4)〜人が感じることは、いつも未来志向〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈5〉
2022/04/12
池見陽先生の「Asian Focusing Methods」セミナーの続きです。
私のフォーカシング・レッスン(4)〜「スペースに生きている」というあり方〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈4〉
2022/04/07
私のフォーカシング・レッスン(4)〜「念」は今の下に心と書く〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈3〉
2022/04/04
理解は心を解放する〜『ブッダの<呼吸>の瞑想』ゆるゆるお茶会〜
2022/04/02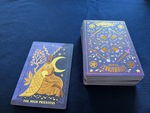
いつものように、最初にタロットカードを引いてチェックイン。
今日の私は大アルカナの「2 女教皇」だった。私のフォーカシング・レッスン(4)〜可能性としての「クリアリング・ア・スペース」〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈2〉
2022/04/01
池見陽先生の「Asian Focusing Methods」セミナーの続きです。
「クリアリング・ア・スペース」
・6つのステップはどんなものか、というのがここに出ているが、ここでジェンドリンの「体験過程理論」で扱っているのは2番目の「フェルトセンス」以降。そこに、「言葉にならない体験」を「フェルトセンス」として、それを表現する言葉を「ハンドル表現」として、一体それは何を伝えているんだろう、何を必要としているんだろう、この感じには何があるだろう、とかそういうことを考えていく、というサイクルがある。これがフォーカシングの中心部分。
・ジェンドリンはどこからか「クリアリング・ア・スペース」という一番目のステップを持ってきた。これは非常に不思議。不思議というのは、本を書く前に論文で発表していることが一般的(そして2から先の「体験過程」のプロセスはたくさん論文がある)。「クリアリング・ア・スペース」については何の論文もなく、いきなり本に登場する。
・しかも、読んでいると、(これは)かなりこなれているやり方。
・ここはフォーカシングの本体部分と異色であって、たとえばフォーカシング指導者のアン・ワイザー・コーネルは、1番目は削除して、本体部分とあまりに違うから、ということでやらない。
・これは一体何かというと、セッションを始める前に、今自分はどんなことが気になっているのか、今どんなことを感じているのか、たとえば、面接に来たクライエントが、話したい話題があって来ているが、来る途中で電車に遅れたことでドキドキしている、そして1日のスケジュールが狂ったことにイライラしている、そういう気持ちを持って来てしまっているので、ちょっとイライラを横に置いといて、その他にどんな気持ちがあるのか、一旦、前に並べて、それらからちょっと距離を置いて、そこから一つ気がかりを選んで進んでいきましょう、とこういうようなステップ。
・おそらくこれは現象学の「エポケー」みたいな意味があるんだろうと思うが、しかし、理論の説明はなく「クリアリング・ア・スペース」が紹介されている。
・日本にこれが入って来たときに、ここが一番、日本人には分かりやすかった部分がある。
私のフォーカシング・レッスン(4)〜フォーカシングとは言葉にしていく過程での意味の形成〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈1〉
2022/04/01
-
 読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休






















