- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- ゲシュタルト療法
- ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(1)
ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(1)
2017/04/30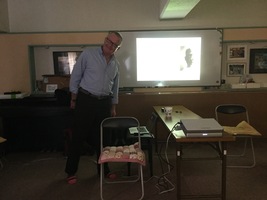
昨日から京橋の平松みどり先生の「みどり会」で、マイク・リードさんによるワークショップが始まりました。京橋のみどり会に行くのが初めてだったので、…そもそも、JR環状線の京橋駅で降りたことがなかったので、駅に降り立った途端、どの出口から出ればいいのかわからなくて、…そうそう、みどり先生、「京橋駅に着いたら、私に電話くれればいいのよ」とおっしゃってた、と思い出し、電話を掛けました。
が、お出にならなくて、さてどうしよう、とタブレットを取り出し、みどり会の住所を入力して、地図で見ました。なんとかナビに頼って、みどり会の場所を見つけました。
(あとでうかがうと、みどり先生、その時、バスで一緒になった90過ぎの男性のお話に引き込まれていたそうな。降りるところを行き過ぎてしまったそう。「あなたがお電話くださった時は、お話に夢中になっている頃ね。」ということでした。…お茶目なみどり先生!)
10時から15名の参加者で始まりました。昨年7月にGNK(ゲシュタルト・ネットワーク・関西)のベーシックトレーニングコースでお会いしてから、9ヶ月が経っているわけですが、お変わりなく穏やかな笑みを浮かべていらっしゃいました。
スタッフが椅子を3列に並べてくれていたのですが、マイクは一列に、そして半ラウンドにするように言いました。それから、なぜこのセッティングが大事なのかの説明から始まりました。(通訳付きです)
「このスタイルにすることで、私とあなた方ひとりひとりとの間に障害物がない状態になる。皆さんひとりひとりが直接的に関われる」
「このスタイルが好きな理由は、(私とあなた方とが)お互いに(直接的に)関わり合えるからです。これがすごく重要だと思っています」
「私とあなた方との間に空間がありますね。(ワークが進むにつれ)この空間が埋まっていく。それをこのスタイルが具現化する」
「質問を受ける方が、学ぶことが多いと思います」
「質問者の質問の中に、『あなた』という人が反映されていると考えます。単に質問に答えるというのではなく」
「何に興味がおありですか? それを基に2日間のワークショップを組み立てたい。」
「伝えるべきことを伝えました、はい、終わり、ではなく。」(※双方向のやりとり、という意味か?)
一連の説明の後、質問受付がありました。
まず1つ目。「ゲシュタルト・セラピーをする上で、大事にされていることは?」
「短く答えるなら『ある』。長く答えるなら、『皆さんが、この二日間の経験を通して理解されたらと思う』」
「私が重視しているのは、その時に『何を』経験しているか、だけでなく、『どのように』経験しているか、ということ。2日間を終えた時に、どのように経験したかを尋ねます」
「ゲシュタルト療法は、分岐点に差し掛かっている。けれど分岐点に立っているのはゲシュタルトだけではない。いかに効果的であり続けるか、というチャレンジに立っているのは他の心理療法でも同じ」
「とても重要なことは、ゲシュタルト・セラピーの理論・方法論をいかに、明確にしていくかということ。私はこのことに情熱を感じています」
2つ目「ゲシュタルト療法への情熱を持つきっかけは何だったのですか?」
「1975年のこと。家族療法のトレーニングをしていた私は、ある時ゲシュタルトのワークに出会った。家族療法の会議の前にワークショップがあって、その中のひとつにウォルター・ケンプラーという人のゲシュタルトセラピーのワークショップがあった。彼は家族の問題をゲシュタルト・セラピーで行うのを得意としていた。5日間、ホテルで行われていた。そのホテルの部屋でウォルターは、カップルや家族に働きかけていた。私はとてもショックを受けた。洗練された、そのワークに」
3つ目「マイクは自分自身のどこが好きですか?」
「ちょっと質問を変えていいですか? 『私はどんなところを好きになりつつあるか?』に変えていいですか?」
「他者と関わる時に芽生えてくる好奇心」
ここで10分休憩。(1時間半が経過していました。)以下、マイクの説明再開。
「ゲシュタルトの基盤となっているものは『違い』。『あなた』は違う人、あなたから見たら『私』は違う人。ここで私の好奇心が動き始める。『違う』二人が出会った。これがカギとなる問いかけです。ゲシュタルトの理論において、共通の理解を求めて確立させるのではない、同意を求めているのではない。『(〜という考え方に)招待している』と考えてください」
「ゲシュタルトの際立った点が最初からあった。それは『健康』『幸福』に焦点を当てているということ」
「人が自然な状態で、どんな傾向を持っているかを理解し、そこから生まれた療法。その基盤として、ひとつが『(人間は)健康を望む、幸福を望む、そしてそれらを追い求める』ということがあった」
「自殺する人もこの世にいるじゃないか!という人もいるが、それは人間の自然な状態ではない。絶望の状態にあったと言える。絶望度があまりにも強くて、健康や幸福の追求ができなかった」
このあと引き続いて、ゲシュタルト療法の特徴を5点説明されたのですが、長くなるので、今日は項目だけ出しておきます。
1 Health/Wellbeing (健康/幸福)
2 Orientation to growth (成長への希求)
3 Organising principle (構造についての大切なこと)
4 Meaning making (世界は意味づけを持った構造物である)
5 Relational (関連性)
さて。昨年7月にはジャンケンで最後になって、私に残された時間は3分間だけでした。マイクの前に立って、3分の時間を味わうというより、「3分だけなの?」という思いが渦巻いて、味わうどころの話ではありませんでした。
今回はワークの時間は2番目で、十分に時間はありました。
マイクの前に椅子を持っていって、かなり近くに座って、じっとマイクの目を見ました。鳶色の穏やかな目がそこにありました。少し悲しそうにも見えるその目を見ていて、なんだか、じんわりと涙が出てきました。…この9か月、いろんなことがありました。けれど、あなたの前に居ると、そんなことはどうでもいいような気持ちになってきます。あなたの存在そのものが優しい。その存在に包まれている気がする。…まあ、これはみどり先生にも少し感じることなんですが。
私の問題は、ないことは、ない。けれど、自分で努力して、なんとかできることはなんとかしていくし、なんともならないことは、そのまま持っていて、でも生きていける、という気持ちでいます。
「私に何かしてほしいことは?」と問われて、迷わず「ハグしてください」とお願いしました。ハグしてもらって、私はもうこのワークを終えていい気になりました。9か月前の「unfinished work(未完了な問題)」が、完了しました。
そして、9か月前に同じワークの場にいて私の3分間ワークを見ていてくれてた人が二人もいて、良かったねと思ってくれていることを受け取れて、私は二重に幸せを感じました。…20分足らずのワークでした。でも私には永遠にも等しい20分でした。
画像はファシリテーターのマイク・リードさん。カラフルなソックスが見えないのが残念。(紳士物には黒、グレー、紺しかないのが不満で、明るい色のソックスを履こう!ということで、「ハッピーソックス」というブランドのものを7年前から買われているそうです。)…そうそう、オーストラリアンイングリッシュは「today」が「トゥダイ」、「can't」が「カント」、「maybe」が「マイビー」、「change」が「チャインジ」でした…。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休






















