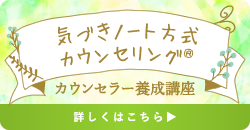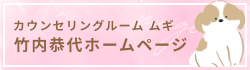- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 対人関係
- 誰が私に言えるだろう 私の命がどこまで届くかを。〜岡田満里子のエッセイ「ぼくを見つけて」〜
誰が私に言えるだろう 私の命がどこまで届くかを。〜岡田満里子のエッセイ「ぼくを見つけて」〜
2018/12/25
今年11月12日付の「毎日新聞」夕刊に、
岡田満里子のエッセイ「ぼくを見つけて」を見つけて、
あっと思った。
私の好きな漫画家のひとり、竹宮惠子の
「ジルベスターの星から」を取り上げてのものだったから。
なかなかいいエッセイだったので紹介します。
「ぼくを見つけて」 岡田満里子
13歳の少年アロウは透き通った不思議な子どもジルと出会う。
実体ではなくて銀河系外の星ジルベスターから、テレパシーを映像化して話しているという。
この交流がきっかけでアロウは科学者となり、ジルベスターへ行く。
そこで見つけたのは、ジルの墓標と移民村の廃墟だった。
病弱なジルの部屋にはコンピューターがあった。
星でたった一人の子どもだったジルはコンピューターに思いすべてを記録させ、13歳で死んだ後も、時空を越えて自分をわかってくれる友を探し続けていたのだ。
切ない友情の物語。
当時、思春期まっただ中だった私は、会話のかけらまで自分をまるごと記憶して、宇宙の果てまで届けてくれる個人用コンピューターに憧れた。
影の薄い生徒で数少ない友達とも本音で話せないと悩んでいたから、揺れ動く気持ちを残らず記憶して伝えることができる装置があれば、いつかそれを見て、ありのままの私を好きになってくれる人が現れるのではないかと思ったのだ。
17歳の私は、なんて傲慢だったのだろう。
私のことは、全記録を読む時間と労力をかけて理解してほしいと思いながら、ほかの人を知るために何ができるかなど思いもしなかった。
自分は何の努力をする気もなく、「本当の私」を見つけてくれるだれかをただ待っていたのだから。
アロウとジルをつないだのは、2人が好きだったリルケの詩だった。
まず相手に興味を持つこと、その人を知りたいと強く願うこと、それが人と人との関係の基本なのは今も昔も変わらない。
40年たって、コンピューターの進化は物語をはるかに超えた。
2017年度の総務省・情報通信白書によれば、国内のパソコンの世帯普及率は73,0%、スマートフォンは71,8%。
インターネットによって出会いの場は、文字通り世界に広がった。
今や多くの人が日々、手のひらの中のスマホでつぶやき、写真や動画を送っている。
「私を知って」「ぼくを見つけて」。
無数の思いが発信され続けるが、それを受け止めようとする人たちはそれくらいいるのだろう。
暗黒の宇宙空間のようなネットの海の中に。
ああ、そうだ…! と思いました。
私も、…14歳だった私も、人づきあいが苦手で、
誰とも本音で話せなくて、
そのくせ、人恋しくて、
私を分かって欲しくて、
だから、コンピューター・ジルが羨ましかった。
私も、「自分を分かって欲しい」ばかりで、
他の人を分かるための努力が必要とは思いもしなかった。
そんな私の転機は、多分、大学に入ってから。
今もずっと付き合いが続く6つ上の友人と出会って。
中国からの留学生で、お母さんは日本人だったけど、
日本古典は知らなくて、授業についていくのに困っていた。
「古典、一緒に勉強しようか?」って申し出て、
1年間、毎週一緒に勉強した。
本当は…行きたくもない大学に進学して、
何の希望も持てなかった私は、
何か人の役に立てることで、
自分が救われたかったのだと思う。
彼女の大陸的なおおらかさに触れて、
だんだんと私は本音で話せるようになった。
「どう思われるか」を心配しないで、
ありのままの私が出せるようになった。
それでも…
パートナーに対しては、
まだまだ「もっと、もっと、私を知ってほしい」が先立った。
だから、このエッセイの「17歳の私は、なんて傲慢だったのだろう。…」のくだりは、
ずんと心に響いた。
そうね。
そうよね。
…だけど、「満たされなかった」子ども期を過ごした者にとって、
やっぱり「私を知ってほしい」が先立つ気がしてしまう。
そうか。うんうん、私は分かるよ…。
そんな風に、満たされなかった子どもを抱えている人を
私は受け入れたいと思います。
「誰が私に言えるだろう 私の命がどこまで届くかを。」は、
アロウとジルをつないだ、リルケの詩の一節。
「ジルベスターの星から」も、その一節から始まる。
14歳の私は、その一節で「言葉」の持つ可能性に心魅かれた。
14歳。
ちょうど私が、ピアノから「書くこと」に移行した時期。
画像は一昨年のルミナリエ。
これほど明るく輝いていても、その光が届くには限界がある。
けれど、「想い」は、「想い」に込められた願いは、
もう少し遠くまで届くような気がする。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休