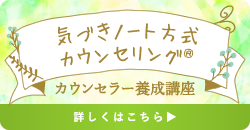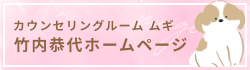- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 言葉
- 水に降る雪 白うは言はじ 消え消ゆるとも〜閑吟集 248番〜
水に降る雪 白うは言はじ 消え消ゆるとも〜閑吟集 248番〜
2020/07/28
昨日は、記憶の中の木琴の音をかき消す雨音、を聞いていたのですけれど、
しばらくそうしていたら、ふと、その音が途絶え、
逆に、音もなく降るもの、に思いを馳せていました。
そう、雪です。
しかも、水の上に降ったとしたら…?
積もりもしない。
…跡形もなく、消え去っていく雪。
水に降る雪 白うは言はじ 消え消ゆるとも
(私の思いは水に降る雪のよう。白いと、はっきりとは口にしません。たとえこの身が雪のようにはかなく消えてしまっても。)
閑吟集。室町後期の歌謡集。一巻。編者未詳。永正十五年(1518)成立。
室町時代の小歌三百十一首を、四季・雑、あるいは四季・恋の順に配列し、さらに春の部が、柳・若菜・松・梅・花…のように連歌風に編集されている。
恋愛歌が中心だが、他に虚無的なもの、民謡的なものも含まれ、当時の庶民の生活感情をよく伝えている。江戸期歌謡への影響も著しい。(「日本文学ガイド」より)
「しろし」は「白し」(=白い)と「著し」(=はっきりとしている)の意味を掛けている「掛詞(かけことば)」。
「消え消ゆる」水に降る雪に、我が身を重ね合わせる。
「消え」は古語「消ゆ」(ヤ行下二段活用動詞・え/え/ゆ/ゆる/ゆれ/えよ)の連用形。
「消ゆる」は連体形。
「消え消ゆる」と重ねることで、降る雪が次々と跡形もなく消え去る情景を描写する。
儚(はかな)げな我が身と、対極にある、想いの深さと。
我が身が亡び去った後も、深い想いだけは残そうとする。…誰が知らずとも。
その、自身の「深い想い」への確かさは、いったい何だろう?
どうしてそうも、疑いもなく一途でいられるのだろう?
…現代人は、自分の気持ちが確かでないから不安になるというのに。
自身の気持ちに揺らぎがないから、不安にもならない、のでしょうね。
自分の心に疑いを持つと、何もかもが信じられなくなって、不安に駆られる。
失敗したくない、愚かでありたくない、と思う気持ちが、自身の在り方を懐疑的にする。
所詮、人は愚かな存在、と、それをそのまま引き受けたら覚悟ができて、
逆に心のままに生きることができるのかもしれない。
画像は昨年8月末の天川村洞川の画像。
雪が降る頃には、道路が凍てついて、この場所には辿り着けないのかもしれませんが、
この透き通った水面(みなも)に降る雪はどんな風だろうと、しばし思いを馳せました。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休