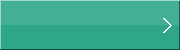- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- セミナー
- シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(1)「公的医療保険」
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(1)「公的医療保険」
2017/07/09
昨日は、シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>を受講しました。
第1講は、「公的医療保険」について。
社会保険制度は「さまざまなことが起きた時、人として生活ができるように社会的に講じておく手段」であり、基本的に「医療・介護・年金・雇用・労災」の5つに分類され、「公的医療保険」はそのうちの一つ。
「医療費&介護費用のポイント」として「生涯医療費の約半分は70歳から亡くなるまで」ということでした。…ふう〜ん、そうなんだ。
「退職後の医療制度」については、既に、昨年度経験済み。
勤めていた時に入っていた「健康保険」の任意継続被保険者になるためには、2ヶ月以上の「被保険者期間」が申請資格ですが、資格喪失日から20日以内に住所地の全国健康保険協会都道府県支部に申請すると、2年間、個人で健康保険の被保険者になることが出来ます。
私も、昨年度、これを申請しました。
なぜなら、要件を満たす家族は「被扶養者」となることを聞いたからです。
ですが、退職後の1年間、特に収入がなければ、「国民健康保険」に切り替える方が、お得。
だって、退職時の収入を基準に「保険料」が決まるから。
もちろん、標準報酬月額の上限が28万円の適応があるんですが、それでも月28万円計算は支払い保険料が高くなります。
それに気づいて、慌てて今年3月末に、共済の「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えました。
「国民健康保険」は「被扶養者」の考えがないとの大原則があるのですが、「被扶養者」が大学生だと違うようで、私の保険料で子どもも入れました。
もちろん、「家族の健康保険の被扶養者になる」という方法もあります。
被保険者と同一世帯にある場合、年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満でないといけませんが。
医療費の自己負担額は、70歳未満は原則3割。70歳以上75歳未満の者は平成26年4月2日以降、原則2割(但し、既に70歳に達している者は1割負担のまま)、70歳以上の現役並所得者は3割。
「現役並所得者」とは、国保の場合、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその同一家族、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上が対象。
高額医療費制度とは、「被保険者や被扶養者が同じ月(1日から末日)に、同一の医療機関(医科・歯科別、入院・通院別)で同一の診察を受け、窓口の一部負担金(保険診療扱い自己負担金)が一定額を超えた場合、請求により超えた分が払い戻される」制度。
自己負担限度額は、月単位で算定されるので、月をまたぐと負担額が多くなります。
これも昨年春、経験済み。
母が4月下旬に入院して、5月初旬に退院し、21日間の入院でしたが、月をまたいだので入院費用が多くかかりました。
高額医療・高額介護合算療養費の合計額が限度額を超えた時は、申請により超えた額が払い戻しされます。
超過分の計算は、世帯内の同一の医療保険ごとで、毎年8月1日から7月31日までの1年間が対象となります。…中途半端な期間の切り方ですね。なぜなのか、質問するの忘れました。
興味深かったのは、「先端医療」の話。
「国が認定した医療内容」かつ「国が認定した医療機関」でないと、先端医療外の治療も含めて全額自己負担となる、ということです。
「国が認定した医療機関」だと、先端医療の部分のみ、全額自己負担なのですが。
それと、「国が認定した医療機関」外では「自由診療」となり、「保険点数の1点の金額を病院で決めてよい」ということで、場合によっては、「国が認定した医療機関」の10割より高くなる、というのです。
また、「保険点数」については、「入院時、2週間までは保険点数が高いけれど、それを越えると低くなるため、病院は2週間で退院させたがる」傾向にあるということも知りました。
退院を早く促されるのは、こういう「事情」があったのですね。
今後の医療保険の動向として、
1 紹介状なしで大病院を受診した場合、平成28年度から5千円〜1万円の追加負担金を払うこととなった。
2 入院時の食費の負担額が平成28年度から1食360円にアップした(以前は260円)。さらに平成30年度から1食460円にアップする。
3 平成30年度から国民健康保険の運営主体が都道府県に変わる。
4 平成28年度から保険診療と保険外の自由診療を併用する「混合診療」の拡大を図る。(患者申出診療)
5 後期高齢者医療保険の保険料は、軽減特例の原則廃止の方向で検討されている。
ということでした。
画像は一昨日の富良野のラベンダー畑。
早咲き品種が満開で、一帯にラベンダーの柔らかい香りが漂っていました。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休