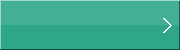- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- セミナー
- シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(2)「高齢者被害犯罪」
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(2)「高齢者被害犯罪」
2017/07/11
前回の続きです。第2講は「高齢者被害犯罪〜その現状と対策〜」。
悪質商法の代表的なものとして3つあって、
1 利殖勧誘事犯(利殖商法)…資金を少しでも増やしたいという願望につけ込み、「社債」「非公開株」等の投機話を装い、「高配当」「絶対儲かる」などウソを言って金をだまし取るもので、詐欺行為がほとんど。
2 送りつけ商法…注文もしていない商品を勝手に送り付けて代金を支払わせる商法。注文した覚えがない代引き商品には代金を絶対支払わない。また、代引きでない場合で注文していない商品を受け取った時は、14日間は使ったり処分をしないようにする。
3 催眠商法…日用品を無料で提供、または格安で販売すると言って店舗などに誘い出し、高額商品を売りつける商法。甘い誘いには乗らない。
悪徳商法の被害の予防は、
1 必ず相手の身元と用件を確認するとともに、インターホン越しに対応するようにして安易に家に入れない。
2 うまい話はそうそうないので、疑ってかかる方が賢明。
3 中途半端な態度は相手に付け入る隙を与えるので、必要のないものははっきり断る。
4 いつまでもしつこい業者は110番通報。
5 悪質業者は口で言っていることと書類に書いてあることが違う。その場で契約書にサインせず、業者が帰ってからもう一度読み直す
6 契約書面を必ず受領する。 7 迷った時は一人で悩まず、信頼の置ける人や警察、消費者センターに相談。
8 契約したとしても、その場で全額を支払うと、後で回収が困難。お金を払うのは冷静になってから。
9 クーリングオフとは頭を冷やすという意味。書面の受領から8日以内に無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができる。(マルチ商法、内職商法は20日以内)
ただし、通信販売はクーリングオフの対象外。また、総額3000円未満の現金取引の場合や、消耗品を使用してしまった場合、購入商品が車の場合、クーリングオフの対象外。
クーリングオフは契約を解除する旨の通知書を作成し、コピーを取ってから業者に送る。
特殊詐欺とは、不特定多数の人に、電話などの手段を使って、対面しないで被害者から金品をだまし取る詐欺の総称で、平成28年度の全国の被害総額は6兆円。
これは国家予算の5%で、国の教育費5.4兆円を上回ります。(!)
特殊詐欺には、①オレオレ詐欺 ②架空請求詐欺 ③融資保証金詐欺 ④還付金詐欺 とあって、
①オレオレ詐欺…「携帯電話番号が変わった」という電話があった場合は、掛け直す。時間を置く。普段から家族や子どもとの間で合言葉などの取り決めをして置く。
②架空請求詐欺…記載された番号には決して電話しない。「法的手続きに移行する」と言われても恐れる必要はない。
③融資保証金詐欺…金融業者は大臣または知事の登録が必要なので、金融庁のホームページで登録の有無が確認できる。名称については、正規の登録業者を装っていたり、休眠会社もあるので確認が必要。
④還付金詐欺…預貯金をしている口座からお金をだまし取る手口で、医療費や保険料がATMの操作で還付されることは絶対にない。最近は、コンビニのATMに誘い出すことが多く、コンビニにと言われたら詐欺。
長くなるので、今日はここまで。
画像は、昨日「絵本講座」に行った生駒市立壱分幼稚園で見かけたトトロ。多分、紙粘土で作られたもの。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休