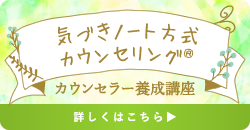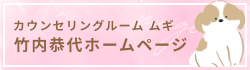- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 長田弘の詩
- 「自分にちょうど」を知る〜長田弘の詩「あのときかもしれない 五」〜
「自分にちょうど」を知る〜長田弘の詩「あのときかもしれない 五」〜
2018/04/11
「あのときかもしれない 五」 長田 弘
子どものきみは、ちいさかった。おとなになったきみよりも、ずっとちいさかった。
おとなの腰ぐらいまでしかなかった。だから、きみは、早くおおきくなりたかった。実際、おおきくなったら、何もかもうまくゆくような気がした。いちいち椅子にのぼらなければ何もできないなんて、ひどく不便だった。どんなものでもみんな、おとなの背の高さにあわせてできているのだ。母親に秘密の話だってできない。秘密の話は、耳うちする話だ。ところが母親の耳ときたら、背のびしても届かないような、とんでもなく高いところにあるのだった。
きみの好きなのは、野球だった。きみはしかし、ボールを片手で、まだきちんと掴めなかった。ボールのほうが、きみの掌よりずっとおおきかったのだ。きみが野球を好きだったのは、きみの父親が野球が上手だったからだ。父親はきみの背の高さとおなじぐらいのバットを、かるがると振りまわした。そして、誰が投げても、いつでもらくらくとおおきな本塁打を打つのだ。
子どものきみは、父親と一緒に、よく野球のグラウンドにいった。グラウンドにゆくのはたのしかった。いつもはこわい父親が、本塁打を打つと、きみのほうをみて微笑した。きみの父親はがっしりとしていた。背が高く、太い腕と速い足をもっていた。きみの父親は、まだきみの父親でなかったとき、名のとおった野球選手だったのだ。草野球で本塁打を打つなんて、簡単だった。
そのときも、きみの父親は、きれいに本塁打を打った。試合はそれで終わりだった。父親はもどってくると、きみに言った、「野球はおもしろいか」
「うん」。きみはこたえた。
「じゃあ、おおきくなったら、お父さんと野球をしよう」。父親が言った。
「ほんとう?」きみはうれしくて、息が詰まりそうになった。父親がきみを仲間にしてくれるというのだ。「じゃあ、ぼく、来週おおきくなるよ!」
来週がきた。しかし、きみはすこしもおおきくならなかった。決心が足りなかったのだ、ときみはおもった。そして、こんどこそきみは、こころに深く決めた。おとなの肩の高さまでおおきくならなくっちゃ。そしてやがて、そのとおり、きみはおとなの肩の高さまでおおきくなった。こんどは、おとなの背の高さまでおおきくなってやろう。そしてやがて、そのとおり、きみはおとなとおなじだけおおきくなった。だが、そこまでだった。どんなに決心しても、きみはもう二どと、それ以上おおきくならなかった。きみは、きみにちょうどの背の高さ以上の人間にはなれなかった。
そのときだったんだ。そのとき、きみはもう、一人の子どもじゃなくて、一人のおとなになってたんだ。これ以上きみはもうおおきくはなれないんだと知ったとき。好きだろうがきらいだろうが、とにかくきみには、きみにちょうどの背に高さしかこの世にはないんだってことに、はじめてきみが気がついたとき。-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休