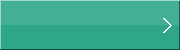- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 心理療法
- 2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー 「発達障害の統合的心理療法(1)加藤敏 先生
2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー 「発達障害の統合的心理療法(1)加藤敏 先生
2017/06/26
昨日は関西カウンセリングセンター主催の、「2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー」に参加しました。
全6回ですが、各回、2名の講師によるそれぞれ1時間45分の講義、事例報告とそれに対する2人の講師による検討が2時間、というメニューです。
第1回は「発達障害の統合的心理療法」というテーマでした。
午前の最初の講義は、加藤敏先生(こども心身医療研究所・主任臨床心理士)。
「発達障害の心理支援における統合的アプローチのあり方」という題名でお話いただきました。
こども心身医療研究所・親と子の診察所の簡単なご紹介があり、「幼児から成人までの範囲で、心因性疾患、発達障害、不登校などに対して主に心理治療、薬物療法を中心に行う医療機関」だそうです。
診療活動を始めてから、今年で31年目に入るとも。
外来治療が中心で、小児科、心療内科、児童精神科を標榜されているそうです。
調べましたら、大阪市西区土佐堀にあるようです。
ご自身の、今から考えると発達障害だったのではないかとお考えになっている、生い立ちの披露からお話を始められました。
どのように「状況理解」が悪かったのか、ひとつの事例のように理解することができました。
ご自身の、学生時代からこれまでに学んで来られた3つの理論(ロジャーズのクライエント中心療法・精神分析的理解+ユング派教育分析・認知行動的介入)をお話しになり、つまりは、それらが現在の「統合的心理療法」にどう関係するか、という流れであったように思います。
印象に残ったのは、3つあって、ひとつは「理論統合」と「理論複合」の違いです。
「理論統合」とは、ある病気や病理に対する心理学的見解を中心にして様々な理論を合成していくもの、ひとつの自己理論を構成するために既存の多くの理論を合成してひとつの理論体系を作ろうとするもので、一元的な姿勢になりやすい、というのです。
それに対して「理論複合」は、患者の悩み、問題などを解決するために、多くの理論や技法をカスタマイズして使用する姿勢で、理論を多元的に使用する認識や態度の在り方を明確にするもので、多元的な姿勢を保ちやすい、こちらの立場に自分は立つ、と。
印象に残った2つ目は、「問題の外在化」というひとつの認識論的方略で考える、ということ。
まあ、カウンセリングは、クライエントが訴える「問題」を仲立ちにして、その問題を共有して解決するように取り組んでいく流れであるのですが、私が興味深かったのは「何が不安なのか、をクライエントが明らかにしようとすることで、『不安』の認識が変化する」と言われたことです。
つまり、漠然とした不安を言語化する流れの中で、「不安に対してキョリが取れる」のだと。
これを、「問題の外在化による距離化」と呼ばれていました。
印象に残った3つ目は、「脳の疲労」という言葉です。
何か問題があるとき、外的要因としての「環境のアセスメント」と内的要因としての「発達をみるアセスメント」が必要だけれど、それがどのように作用して問題を引き起こしているのか、すぐさまはわからない。
それより、現象として「脳の疲労」が起こって、症状や問題行動を引き起こしているのだから、まずは「脳」を休めることを行うべきではないか、という見方。
緊張状態を和らげ、心を落ち着かせ、という関わりの必要性を言われているのだと思います。
分析は必要。ですが「緊急事態」に必要なことは、分析から導かれる対応ではなく、緊張状態を解き、心を落ち着かせること。
まあ、あたりまえと言われるとそうですが。
逆に、「あたりまえ」な対応をすべき、ということかと。
今回、新たに知ったのは「パニックや怒りの爆発にはピーク点があり、ピーク点の手前で落ち着かせようとしても、なかなか怒りは収まらないし、逆に長引く」ということ。
これも言われてみるとそうだなあと思うのですが、「怒り」に対して良くないものという見方をしていると、とにかく「やめさせないと」に走りがちでしょうね。
始まったら、一定時間エネルギーを放出させる方がいいのでしょう。
薬物療法に対しては「保護者に対して、なぜ薬物療法を勧めるのかというきちんとした説明は必要だけれど、基本的に、嫌がっている保護者には勧めない」とのご説明があったので、「どういったときに薬物療法をお勧めになりますか?」という質問をしました。
「生活が成り立たない」「暴力が出る」場合に、とのお答えをいただきました。
臨床の現実として、良くなったと納得がいったケース、つまり今回紹介したようなケースは全体の3割、なんとなくいいのかな?程度に終わったのが3割、うまくいかなかったのが4割、ということを言われました。
非常に率直なお話をしていただいた、と思います。
画像は朝の杏樹(アンジー)との散歩で見かけた、ご近所の居眠り天使。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休