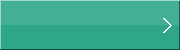- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 心理療法
- 2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー「発達障害の統合的心理療法」(2)村瀬嘉代子先生
2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー「発達障害の統合的心理療法」(2)村瀬嘉代子先生
2017/06/27
加藤敏先生の講義のあと昼休憩となり、午後からは村瀬嘉代子先生の講義となりました。
村瀬先生は、大正大学大学院にお勤めで、今年3月まで、日本臨床心理士会の理事長をされていた方です。
昨年度のKSCC統合的心理療法セミナーでも講義されたことを思い出し、1年の時間経過の速さをふと感じました。
村瀬先生の講義で印象的だったところを列挙してみます。
発達障害とは、人間の一生にわたって身体・知・こころの面に現れてくる成長・変容の過程において、何かしらの「負の様相」が人生の早期に現れ、それが一過性なく、その後の成長・変容に何らかの影響を持続的に与えている状態。
障害と呼ばれる様相は、生物学的脆弱性と、心理療法・社会・文化的要因が輻輳して関与している。
援助の視点はそれらの様相の全体像を捉えつつ援助過程の状況に応じて、焦点化をも併せ行うこと。
臨床においては「一人称」、「二人称」、「三人称」(=対象化して捉え直す視点)の視点を併せ持つ上での理解と対応を元に、身を添わせることが望ましいのではないか→セラピストのバランス感覚
援助とは基本原則を踏まえながら、個別的で多面的なアプローチをすること。
綿密に気づき、観察し、考え抜き、工夫すること。
発達的視点からの理解として、問題行動はその子なりの適応しようとする営みである。
発達障害児を理解するということは、人の発達がどのように生物学的、心理的、社会的要因によって影響を受けているかを解明すること。
「問題」と言われる行動にも、複数の経路や経過がある。
支援者に問われることは、自分自身の障害観、人生観。
「ある条件を受け止めて、限定される枠を模索努力しつつ、広げていく生」
家族やその他周囲の環境に対して、共同援助者という立場で(咎め、糺す眼差しではなく、ささやかでも分かちあう)、上下関係ではなく、一緒に。
困難に遭遇することで、家族関係の瑕疵(かし=不十分な点 ※引用者注)が表面化し、それが療育過程に陰を落とすこともあり得る。家族関係の維持・向上を念頭にそっと置く。
家族とは双方向性を持って、親の希望に添いながら情報を共有して進める。
きょうだい、近隣との関係への配慮、きょうだいにも配慮を。
療育場面やセラピーの場面と日常生活の連続性を考える。
訓練という色彩に終始しない。楽しさ、歓び、ユーモアの感覚をどう見出すか。
身体的ケアと心理的ケアのバランス
「ある条件を受け止めて、限定される枠を模索努力しつつ、広げていく生」と打っていて、それは、障害の有無に関わらず、誰もがそうなのではないか、と思えてきました。
私は「長女」として親から要求されることが嫌で、ずっと避けてきた。
避けて四半世紀を生きて、自分の人生を振り返ってみた時に、さほど「幸せ」ではないことに気づいた。
ならば、それを引き受けた時に、自分の人生はどう展開するのだろう? と思った。
それはある意味「ある条件を受け止めて、限定される枠」を受け入れたことではないのか? と思うのです。
そして、その枠を「模索努力しつつ、広げていこう」として、「カウンセリングルーム」を開き…という今があるのではないか…?
とすると、障害を持つ人と私とは対岸にいるのではなく、「生きづらさ」「息苦しさ」の点において、共感できる素地がある、と思うのです。
…まあ、そもそも強度の近視なので、そういった意味でコンタクトレンズやメガネなしには生活が全く成り立たず、自分の状況に合わせて「工夫」しながら生きているという点で共通項を感じてきたのですが。
できることを、できる時に。無理なく。
そう思います。
さて、村瀬先生が言われたことで、一番印象的だったのが「関係というのは、会った瞬間から、別れる時まで。カウンセラーがアセスメント(査定)をすると同様、クライエントもカウンセラーのアセスメントをしている。関係は双方向的。」
それはそうですね。クライエントは必死になって「この人に話して大丈夫だろうか? 傷つけられないだろうか?」とカウンセラーの人となりを探る作業をしている、と思います。
その後、事例として「ある少女が生きる喜びを見出すまで」をお話くださったのですが、出会いから40年を経た、その関わりは圧巻でした。予定時間を遙かに超えて、でも、先生のお話に聞き入りました。
支援とは本当に、共に生きること、と痛く感じました。
私もそういう支援をしたいと願います。
そうそう、先生はかなり高齢でいらっしゃるとお見受けしたのですが、なんと82歳でいらっしゃいました。
画像は朝の杏樹(アンジー)との散歩で見つけたご近所の赤いお花。見かけない花でしたが、ちょっと可愛い。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休