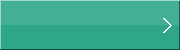- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 教育
- 白庭台幼稚園だより(2)
白庭台幼稚園だより(2)
2017/07/14
昨日は白庭台幼稚園の「保育観察&担任相談」の日でした。
1学期の最後の相談日なので、そして、来週に保護者との個人面談があるようなので、保護者への対応についての相談にも乗りました。
そんな中で質問されたのが、自分からお友だちの中に入っていけない子への対応です。
自分から「入れて」って言えない子に、「自分で言わなきゃ…」と指導するのは、その子にとってハードルが高すぎる。
それより、お世話好きの子に「◯◯ちゃんを誘ってくれたら、先生助かるなあ」という形で、まず、周囲への働きかけをする。
で、お世話好きの子にもありがとう、と声かけしつつ、声かけしてもらった子の様子を見る。
何回か繰り返した後、今度は、◯◯ちゃんに「今度は自分で言ってみようか?」と働きかける。
それも、誘ってくれたお世話好きの子に。
そうすると、断られる心配がなくなっているから、「自分から声をかける」というハードルもずいぶん低くなっているはず、と。
そういう「スモール・ステップ」の設定が、「できない!」と尻込みさせないで乗り越えさせる方法だと。
そして、その子だけでなく、周りも一緒に変わっていけるチャンスにできる、と。
もうひとかた、「大人との関わりばかりを求めてくる子をどうすればいいか」という質問もありました。
…いるんですよね、高校生でも、同学年との付き合いが苦手で、教員とばかり話したがる子って。
同世代は「配慮」してくれないので、そして教員はいろいろ「配慮」してくれるので、その子にとってラクなんですが、同世代集団の中で浮いてしまう子です。
何か、お友だち同士でトラブルがあったとき、近くにいても「自分は知らないよ!」とまず予防線を張るようです。
ですが、トラブルのいきさつをよく見ていて、説明もしてくれるそうです。
「だったら、そこを『入り口』にしましょう」と私は言いました。
「◯◯ちゃん、よく見ていてくれて、それで先生に説明してくれるから、助かるわ」とまず褒める。
それを何回か繰り返した後、今度は「◯◯ちゃん、どうしたら、お友だちが喧嘩せずに済むかなあ?」と尋ねてみる。
「きっと、譲ってあげたらいい、と答えると思いますよ」と担任の先生からお答えがありました。
「そうですね。そうしたら、◯◯ちゃんが、そう言ってあげてくれない? という働きかけをしましょう」と言いました。
そうすることで、第三者的に集団から距離を置く子を中に引き入れることができる、と。
今回、「高校生でもそういう子がいるんですよ」とお伝えできたのが良かったと思います。
今、取り組むことが、将来の、その子の在り方を変えるかもしれない、という視点は、幼児教育に携わる者が持っていた方がいいと考えるからです。
幼児教育の大切なところって、そういうことですよね。
日常の、ちょっとした周囲との関わりが、その子の価値観の基礎を作る。
考えてみれば怖いことだと思います。
そういう畏怖を抱きつつ、願いを込めて、子どもと関わる。それが大事と思います。
画像は、年少さんのクラス風景。お顔が写らないように気をつけました。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休