- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- フォーカシング
- 私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(4)
私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(4)
2017/08/02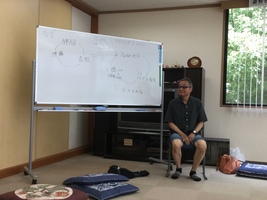
最初のセッションの後、「クリアリング ア スペース」の説明がありました。
「クリアリング ア スペース」とはフォーカシングの技法の一つなのですが、どこから来たものかはわからない、と言われました。
フォーカシングが影響を受けた「現象学」では「括弧に括る」というそうです。
つまりは、いろんな「気がかり」から間を置くこと。
「間が置けない人を『間抜け』と言うんですよ」という余談付きの説明に、なるほど! と一同うなづきました。
「クリアリング ア スペース」のやり方(いろんなやり方があるうちの1つ)
1 「そのことを思うと、どんな感じがするか? 感じてみて」と「ことがら+感じ」を出してもらう。(フェルトセンスとして感じてみる)
2 「そのことを、ちょっとの間、置いておくとしたら、どこがいいでしょう?」と、ちょうどいい場所を見つけてあげるよう促す。見える場所の方がいい場合もそうでない場合もある。「捨てる」類いはいまくいかない。たとえば、海に捨てたとしたも、また、海岸に打ち上げられたり、と返って来たりする。どんな感情も「自分の気持ち」だから大切に扱う。(適切なキョリを見つける)
3 「他にありますか?」という声かけで、次々と自分の「気がかり」に対して、適切に置ける場所を探していく。
「どうしても置けない場合は、どうすればいいですか?」という質問がありました。
その場合は「置けないことに気づく」ことが大事で、「それを置けない自分はどんな自分?」と「観我(かんが)」に向かうか、「それはどこに行きたがっていますか?」と「もの」に主導権を渡す。
それでも置けない場合は、「そんな気持ちがあったことに気づいておきましょう」と「置けない」自分を受け入れる。
「クリアリング ア スペース」を行うと、出してもらう「ことがら」の、具体的な中身が問いかける人にわからなくても、その「ことがら」を出している人は、それとのつきあい方が変わるので、問題そのものが変わる。
つまり、「悩み」とは「悩むこと」ではなく、それとのキョリが取れないことが問題なのだ、と。
「クリアリング ア スペース」とは、「心の中を片付けて、空間を作ること」である、と。
高野山でも「悟りを開きたい人は部屋を片付けなさい」と言われるそうな。で、実際に部屋の片付けをするそうです。
心理現象と物理現象は繋がっているのだな、と思いました。
確かに。散らかった部屋にいると心が荒んでいくし、精神衛生上も良くないんだ、と。
「クリアリング ア スペース」を初めて私に教えてくださったのは有村凛さんでしたけど、その時は画用紙を使って、でした。
私は、視覚化されるこの方法が、結構気に入っているのですが、画用紙がない場合でも「クリアリング ア スペース」が出来るんだなあ、というのは発見でした。
イメージ化が苦手な人には、視覚化できる方がやりやすいかもしれません。
人にもよるし、状況にもよるんですが、やり方が増えたのは嬉しいことです。
さて。初日はここまでで、2日目の最初の時間に、ジェンドリンの「フォーカシング 6ステップ」の説明がありました。
ジェンドリンの「フォーカシング6ステップ」
1 「クリアリング ア スペース」
2 フェルトセンス
3 ハンドル(見出し・手がかり)表現をみつける
(ハンドル表現=この言葉で表現すると、なんとか全体がつかめる、という言葉)
4 ハンドル表現をリゾネイト(響かせる・確保する)する
5 (理解のための)問いかけ(6つ)(「もやもや」はフェルトセンスの例)…その場にふさわしいものを選んで使う
① この「もやもや」はあなたに何を伝えているのでしょうか?
② この「もやもや」はいったい何でしょう?
③ その状況の何が「もやもや」みたいなのでしょう?
④ この「もやもや」は何を必要としているのでしょう?
⑤ この「もやもや」とかけて、その状況ととく、その心は? (なぞかけ)
⑥ 「もやもや」と一緒にいましょう。何か浮かんできますか?
6 受け止める
この6ステップは直線的に進むのではなく、2→5については、何回かグルグル回るイメージ。
そして、この2→5のサイクルを回すことが大事で、うまく回らない時に、「5」の6つの問いかけがあるのだと。
フェルトセンスが強い感情となってきたら、少し遠ざける。
その時の声掛けは「ちょっと遠目に見てみましょう」。
他に…「この辛さは、私にとってどんな意味があったのだろう?」「この辛さはあなたに何を伝えたいのだろう?」などの声掛けで、サイクルが回る、と。
内省力が弱い人には「プレセラピー」が必要である、とも言われました。
「感じること」を予め、「教育する」のだそうです。
池見先生は『傾聴 心理臨床学 アップデートとフォーカシング』という最新のご著書(2016年3月)のpp.130-131をコピーして配布してくださったのですが、そこには「5つの問いかけ」が記載されていました。
…つまり、出版されてから、この半年足らずで、6つ目の問いかけが増えたのですね。
常に「より良いもの」を求める、先生の姿勢を感じました。
さすがに、今日はここまで、でしょうね。
画像は2日目の池見陽氏。グラサン・短パン姿での登場にちょっとびっくり。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休























