沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。
あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。
カテゴリーごとに選べます。
絵本の世界
月の光だけで撮影された写真集〜『月光浴』石川賢治〜
2017/04/19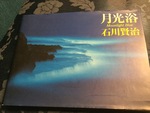
写真集です。それも「すべて満月の光だけを光源として撮影された。」と最初のページにあります。続いて最初のページには「月は、地球のただ一つの自然の衛星。地球にもっとも近い天体である。」とあります。
続き
1990年11月に第1刷の発行です。私が買い求めたのは1991年2月。もう第5刷となっていました。(よく売れたのですね。)小学館から出ています。
アンジーとの暮らし
杏樹(アンジー)との朝の散歩
2017/04/18
昨日は、コラムを書き上げたあと、ちょっとまだベッドに横になっていたので、いつもの散歩の時間より遅くなりました。ようやく起き上がった私に、先にベッドから降りていた杏樹(アンジー)は、背中を丸めて前足を伸ばし、次に後ろ足を伸ばして、「さあ!行こうよ!」というふうに「うおん」と言って、準備していました。
私が毎朝「アンジー、おはよう! アンジーも、『ママ、おはよう!』って言ってごらん。」というものだから、くしゅん、と鼻を鳴らして、一生懸命「うおん」と言うわけです。「ほうら、アンジー、『お散歩行きたいよー』って言ってごらん。そしたら連れてってあげるから」などと私が言うものだから、アンジーも一生懸命「うおんうおん、うおおん」と話し始めます。…ということで、うちのアンジーは話せます。
不思議なことに、私が2、3日家を空けて帰ってきた時などの「文句」口調と、朝起きた時のご挨拶とは、明らかに違っているのです。…やっぱり、用途に応じて「おしゃべり」するんだね。
「パピー教室」では、ワンコにリードを引っ張らせてはいけない、どこに行くかは飼い主が決める、と教わりましたが、それで、そのようにしていたのですが、でもまあ、朝夕の散歩ぐらい、アンジーの好きなところに行かせてもいいような気がして、このところ、「アンジー、どこ行きたい?」と聞いてやっています。いつものコースだと、ちょっと飽きるみたいで、時折コースが変わります。
リード、などと言い換えてるけど、「鎖」よね…と思っていたのですが、近くの公園で、いつ他の人が来るかわからないのでリードを外すわけにはいかないけど、リードをつけたまま好きに走らせてやろうとしたのですが、なかなか動かない。私がアンジーから遠ざかって、そうして「アンジー!」と呼ぶと、やっと動き出すのです。…それより、私と一緒に走りたがるのですが、それは限界があって、私はすぐにバテてしまいます。
今朝は、自分の行きたい方向にグイと引っ張って主張するアンジーに、リードはもしかするとアンジーには「鎖」ではなくて「絆」なのかな、と思ってしまいました。自分の意思が通ると、もう引っ張るのをやめるのです。まあ、ワンコは「永遠の3歳児」などと言いますから、自分の意思を主張しながらも、見守っていてほしいのですね。
人の子は…、いずれ自立して、自分の意志で生きていきますけれど。あ、でも、リードが長く長くなって、何百キロと離れても、見守っていてほしい感覚はあるのかもしれない。
そんなことをつらつらと考えた朝でした。
画像は、尾道で撮ったアンジー。遠くを見ていました。(なんか、哲学的…)
ゲシュタルト療法
ゲシュタルト療法トレーニングコース最終回(3)
2017/04/17
GNK主催の「ゲシュタルト療法トレーニングコース」の最終回も、いよいよ最終日を迎えました。前日と同じく、朝5時半過ぎからの本堂での「朝のお勤め」に参加し、再び「戒壇巡り」をして、もう一度「生まれ変わる」体験をし、引き続いての千手院での「朝の護摩焚きお勤め」にも参加して、一日が始まりました。
朝のワークは9時開始で、簡単なチェックインの後、「夢ワーク」に取り組むことになりました。最初に百武さんから受けた「夢ワークのやり方」は次のとおりです。
<夢ワークのやり方>
1 「どんな夢を見ましたか?」から始める。
2 ある程度全体像がつかめたら、「あなたの目の前の『夢の扉』を開けて、実際に夢の中に入って、現在形で語ってください」と声掛けをする。
3 焦点を当てるところを決める。① ファシリテーターが焦点を当てたいところを選ぶ。 ② 「印象的な場面はどこですか?」とクライエントに聞く。
4 夢に出てきた人、動物、家、風景など、「そのものになってみる」ことを提案し、「私は〜です。」という言葉で、何かになってみて、見えることや感じることを話してもらう。夢の中に出てきた人物に対話させてもよい。(サイコドラマ風に。)このようにして、「全体像の私」に気づく。(色、形、人物、もの、風景は、すべて「私」である)
5 「夢」に対するファシリテーターの立ち位置として、1つは「その人が体験していることの未解決なものである」という立場と、もう1つは「夢は自分が投影しているイメージで、言葉で表現できないものを象徴的に体験している」という立場があるが、その都度変えていくのではなく、どちらかを自分で選ぶ。(いずれにせよ、答えを出すのではなく、自分の人生の指針としてシンボリックに受け取る。)
クライエント役1人に対して、ファシリテーター2人(そのうちの1人が私)という形で、CFO体験を行いました。ついつい、「現在形で語ってもらう」「夢の中に出てきた何かになって、そのものとして話してもらう」ことを忘れて、ちょっと混乱しました。
軽く昼食を取った後は、なんと! 70を過ぎた百武さんが、バンジージャンプに挑戦!ということで、メンバーは動画撮影やら写真撮影やらに奔走して、誰も後に続いてバンジージャンプには挑戦しませんでした。(みんな、エリカ・ジョングではないけど「飛ぶのが怖い」状態だった…)
無事終了して、ヤレヤレ、だったのですが。(私は写真を撮るのに橋の上から下を覗くだけで、なんだか足裏がムズムズしてくる感じがした…。)
一連の流れ(飛ぶ前、飛んでいるところ、飛んだ後)は、百武さんのHP内のブログでアップされるとのことです。お楽しみに。
バンジー騒ぎで、ちょっと疲れて、午後のワーク再開は2時となりました。
「何をやりたいですか」とファシリテーターに促され、私はとりあえず、百武さんの前に座りたくなりました。これといったワークのテーマがあったわけではないのですが、百武さんの前に座り、内部領域の気づきを言うように声掛けされて、それを行い、次に外部領域の気づきを言うように声掛けされて、それを行い、ゆっくりと周囲を見渡して、「いろいろ抱えている問題はあるけれど、でもまあ、いいや、という気持ちになりました。」と言って、ワークは終了となりました。
私の抱えている問題は、まだいろいろあるのだけれど、その問題を抱えたままで、でも私はやっていけそうな気がしたのです。こういう感覚が、生きていく上で大事な気がしました。「私には抱えている問題がまだある。そして、その状態で私は生きていける」。(ゲシュタルトでは、「but でも」ではなく「and そして」を用いるんだ、と言われたことを今思い出しました…。)
3日間、とても豊かな時間でした。そして、トレーニングコースの1年間もとてもとても豊かだった。百武正嗣さん、メンバーの皆さん、そして主催者のかずりんこと白坂和美さん、ありがとうございました。
画像は最後にみんなで書いた寄せ書き。(百武さんが中央に「空とぶゲシュタルト」と大書きしました…!)
ゲシュタルト療法
ゲシュタルト療法トレーニングコース最終回(2)
2017/04/16
GNK主催、「ゲシュタルト療法トレーニングコース」合宿の2日目、朝5時半から本堂での朝のお勤めに参加し、引き続いて本堂の「戒壇巡り」をしました。これは、お寺によっては「胎蔵界巡り」と呼ばれているものです。
「胎蔵界」とは「密教で説く二つの世界のひとつで、金剛界に対して、大日如来の理性の面をいう。仏の菩提(ぼだい)心が一切を包み育成することを、母胎にたとえたもの。」(デジタル大辞泉)とあります。(ちなみに「金剛界」とは「密教で、大日如来の、すべての煩悩(ぼんのう)を打ち破る強固な力を持つ智徳の面を表した部門。」(デジタル大辞泉)だということです。)
本堂の地下に、暗闇の中ぐるりと一周回れるようになっていて、塗香(ずこう)を手のひらに塗って、右手で壁面を触りながらゆっくりと一周しました。…私は、胎内に一旦戻り、産道を通って、また、生まれ出たきた感じを持ちました。
その後、千手院に戻り、ここでは護摩焚きをしながらの朝のお勤めがありました。般若心経その他を一緒に唱和しながら、最後に「毘沙門天護摩祈願」をひとりひとり受けました。
6時45分からの朝食の後、午前のワークは9時からでした。CFO(クライエント・ファシリテーター・オブザーバー)体験を始めるにあたって、ファシリテーターの百武さんから3点、説明がありました。
<CFO体験での注意事項>
1 ストーリーに乗っからない
「ストーリー」とは本人の説明。それは本人が「解釈」していることで、そのストーリーに乗っかってしまうと、本人の「自分の中のサイクル」が回り始めるだけで、そこから抜け出せない。
2 「気づきの3つの領域」に問いかける
「 3つの領域」とは、「外部領域(現実の世界)」「中間領域(思考レベル)」「内部領域(からだ)」。思考をストップさせるのは、思考が悪いわけではなく、偏っているからよくないだけ。感覚・感情に目を向けさせることで全体像に近づこうとする。
3 何かを変えようとする必要はない
3つの領域に目を向ける「問いかけ」をすることが必要。ゲシュタルトでは「十分に経験する」ことをする。解釈しないで、(痛みなど)治そうとしないで、今感じている感情や痛みを十分に味わう。「十分に経験する」ことが「気づく」ための大事な条件。
9時半から始まった朝のCFO体験では、2人ずつペアになり、25分ずつファシリテーター役とクライエント役になりました。「エンプティー・チェア」を使う方法で行い、テーマは「自分を育ててくれた人」でした。「エンプティー・チェア」技法を用いるのあたっての注意事項は次の3点。
<エンプティー・チェア技法>
1 人物像がファシリテーターに明確になった時に、エンプティー・チェアを置く。
2 その人がいるように、少し時間を取る。
3 1つの話題、1つのできごとに絞る。
なお、ワークのための「気づきの4つの問いかけ」は次の4点。
<気づきの4つの問いかけ>
1 今どんなことに気づいていますか?
2 身体の中で、何が起きていますか?
3 あなたのしたいことは何ですか?
4 気づくことをどんな方法で止めていますか?
さて、午前の部で私が学んだことは、「どこでワークを終えるべきか」ということでした。
私のクライエント役となった人が「自分を育ててくれた人」として母を挙げたのですが、話し始めると、母との葛藤が出てくる。
百武さんに「ファシリテーターとして、このまま続けるか、やめるか、どちらを選択するか」と問われ、「テーマとは離れるけれど、クライエントにとって大事なことのように思えるから、続けます。」と答えたのですが、その判断は誤りでした。私は「情」の部分で動いてしまったように思います。けれど百武さんが指摘したのは「自分を育ててくれた人として母を出したのに、母との葛藤が焦点化されている。これが、1つの課題となっている。(クライエントにとって)どういうことが自分を育ててくれたかが明確になると、問題はクリアできる。でも、今のままだとループになって(葛藤が)強化されるから、やめたほうがいい」ということでした。
その「やめ方」としては、「ファシリテーターが、今起こっていることをクライエントに説明してグランディングすること」と言われました。そうして「断つ」のだと。
午後のワークは、1時半過ぎからの「滝行」の後、3時から始まりました。今度のCFO体験は「エンプティー・チェアを使わない方法」で行うものでした。エンプティー・チェアを使わないで、ファシリテーターに対して「私がその人だと思って、言いたいことを言ってください」という声掛けをして、クライエントが内に閉じ込めていたものを外に表現するように働きかけるのだということでした。テーマは「自分の苦手な人」。
「いつ、どこで、何があったのですか?」という問いかけで「外部領域の気づき」を促し、「そういうこと、そういう人に対して、何を感じていますか?」「どんな気持ちでいますか?」「どういう風に伝えたいですか?」という問いかけで「内部領域の気づき」を促すのだということでした。
私が苦手な人として取り上げたのは、母でした。母が絶対的に苦手、というわけではないのだけれど、時折とっても嫌になってしまうということで。「いつどこで、何がありましたか?」に対して、「今回の合宿に参加するために家を出る時、ちょうど宅配が来て、なんだろう?と思って中を確かめて、その後、家を出る時間が迫って来たので、宅配のダンボールを折り畳んでゴミ置き場に片付けないで、玄関の靴箱の上に置いておいたところ、母が『また、最後まで片付けないで置いてる!最後、もうひと手間片付けてくれたら、私の手も煩わされないで済むのに。」と言ったことに私は腹を立てて、『何で、それを今言うの? 私は今、出かけようとしているところなのよ!』と言ってしまった。」という話をしました。
CFO体験で私は「過去に母が自分の気持ちを優先するばかりで、私の気持ちにお構いなしに言ってくることが多くて、それも自分の価値観、感覚を絶対的なものとして押し付けてくることに、イラっとしてしまう。子どもの頃の私は何も言えなくて。大人の私は言えるようになったのはいいんだけど、過去の『未完了な問題』が蓄積されているから過剰反応してしまうのかなあ…」と思ったところで、タイムリミットとなりました。
このワークについて、ファシリテーター役の人が、「(クライエントに)感情を出させた後、どう関わっていいのかわからなくなって…」というシェアをしたので、それは他の人も自分のファシリテートに感じていたことだったので、みんなの前で再現することになりました。
母に片付けるように言われた私が感じた感覚、胸の方から喉元に湧き上がってくる「グワッとした」感覚、そして「またかい!」という言葉、それをもっと感じるようにと百武さんに言われました。何度か右手で胸から喉元に何かが突き上げてくる動作をしながら、その時の感情を思い出していると、突然、「ギャー」か何かわからない声とともに右手が何かを襲うような、仕草になりました。即座に百武さんに「何かに襲いかかっているようだね」と言われ、その右手で、私は母を捉えようとしていたんだと思いました。その瞬間、私の口から出た言葉は「私は母をまだ許してないんだ…」でした。
『トレーニングテキスト』には「気づきのサイクル(経験のサイクル)」として「0」から始まり、次のような流れでサイクルが示されています。
<人が水を飲みたくなるプロセス>
Sensation(感覚)→Awareness(気づき)〈図形成〉→Mobilization(行動に移そうとする)→Action(取りに行く)→Contact(水を取る)〈現実にあるもの、人〉→Assimilation(水を飲む)〈統合、消化〉→Withdrawal(引きこもり)〈うるおう〉→ 0
百武さんは、このサイクルの良さは「どこで止まったかで、問題が説明できる」ということだと言われました。私の場合は、「Contact」の部分が問題で、「片付けたくないのに、片付けるように介入される」ことにイラっときているのだとわかりました。つまり、私が考えたように「過去の未完了なことが問題」なのではなく、「今ここで起こっている母の侵入」が問題だったのです。「過去の未完了なことが問題」と思ったのは私の中間領域の「解釈」に過ぎなかった。…これには本当にびっくりしました。自分の感情を味わい続けていると、自ずと答えが出るのですね。私は母の、私に対する「侵入」に対して、怒りを感じていたわけです。なぜ、私のペースでなく母のペースで「片付け」のタイミングを決められなければならないのか、と。
百武さんから「ここでワークを終えておきましょう」と言われました。「私は母を許していない」という気づきを得たわけだから、それから先に進むのではなくて、それを十分味わうように、とのことでした。
私は母はこういう人だから、と諦めているつもりだったのです。そういう母を認めて受け入れようとしているつもりだったのです。しかし、そうではありませんでした。「なぜ、あなたは自分の感情ばかりを優先して、私の気持ちに気づこうとしないのか?」それが私の正直な気持ちでした。
いやはや、ゲシュタルトは、まだまだ奥が深いですねえ。CFO体験で初めて見えてくるものもあります。いつぞや平松みどり先生がおっしゃった、「よくもまあ、ゲシュタルトというヤクザな道に。もう、ちょっとやそっとで足を洗えませんわよ。」が頭の中で響き渡ります。
画像は、今朝も昨日に引き続き、5時半の本堂でのお勤めに参加する前に撮った日の出。ちょっと雲がかかりました。
<追記>
エンプティー・チェアを使わない方法で、ファシリテーターに向けて「怒り」を放出させるためには、ファシリテーター自身が自分の問題を解決していないと「怒り」に対して対処できない。ということは、エンプティー・チェアを使わない方法はファシリテーターができるようになっているかどうかの指標になるのだろうか、ということをちょっと考えました。百武さんに質問し忘れたので、次の折に確認しようと思っています。
ゲシュタルト療法
ゲシュタルト療法トレーニングコース最終回(1)
2017/04/15
昨年4月から受け始めた、GNK主催の「ゲシュタルト療法トレーニングコース」もいよいよ最終回を迎えました。最終回は二泊三日の合宿で、昨日午後1時に「現地集合」だったのですが、「現地」はなんと信貴山千手院の宿坊です。
信貴山は「張り子の虎」で有名で、何度か訪れたことはありましたけど、宿坊は、初めてでした。山の斜面を利用して建てられているのか、玄関から入って階段を降りたところの1階のお部屋を4室用意していただきました。部屋の外に廊下があり、大きな中前栽がしつらえてありました。お庭に面してはガラス戸になっているのですが、そのガラスときたら、昔懐かし「ものが歪んで見える」硝子でした…!(私の子どもの頃は、こんなガラスだった…)
さて、初日は、まず理論の整理から。「トレーニング・テキスト」をおさらいする形で、順番に振り返りをしていきました。テキストから抜き出す形で整理します。
ゲシュタルト療法とは
精神分析医フリデリック・S・パールズとゲシュタルト心理学者であった、ローラ・パールズ、そしてポール・グッドマンによって創られた「今、ここ」での気づきを重視する「実践的な心理療法」。
ゲシュタルト療法の創始者であるF.S.パールズが影響を受けたのはフロイトの精神分析、ゲシュタルト心理学、実存主義、現象学と東洋の禅。
ファシリテーター百武正嗣さんの説明で、「パールズは日本にも来て禅を学んだけど、日本の禅のシステムは、『禅坊主』を作り出すシステムで、それは、西洋の『精神分析医になるシステム』と非常によく似ている。」「一生かけて、悟りが開けるかどうかわからないなんて、システムとして非合理的。だから『悟り』でなくて『ミニサトリ』でいいとパールズは考えた」という言葉が、印象に残りました。あと、「身体への問いかけ」の理論的枠組みを作るのに影響を受けものとしてウィルヘルム・ライヒの「筋肉の鎧」、「センサリーアウェアネス」と名付けられる前の、ジュディスの先生であるシャーロットの身体へのアプローチ、フェルデン・クライスなど。
身体中心型療法〜ウィルヘルム・ライヒ〜
フロイトがウィーンに1922年、精神分析診療所を設立した時に、臨床助手の第1号となった。後に彼は多くの分析医の指導にあたるとともに彼らの個人分析も行なった。フリッツ・パールズもその1人でありライヒの身体中心型の心理療法の影響を受けた。
ライヒの心理学への貢献は次の3点である。
1)精神と身体の調和を強調したこと。
2)心理療法に身体のを含めたこと。
3)「性格の鎧」の概念。→のちに、「筋肉の鎧」に改変
ライヒの有名な「性格の鎧」という概念は、人間の慢性的な筋肉の緊張がどのように個人の歴史の中で形成されていくかを示したものである。ライヒは<個人の性格>はそれに対応する<身体的な態度>があるということを強調したのである。人の性格は、筋肉の硬直と関係がある。人は様々な感覚(怒り、快楽、悲しみ、性的感覚)を感じるわけであるが、それを自由に表現することができない時、または表現することが危険を伴う場合には、その感覚や感情を抑圧しようとするために筋肉を緊張(硬直)させてしまう。
その防衛的な<身体的な態度>が、性格の鎧であるとした。ゲシュタルト療法では抑圧していた感情や感覚に気付いた時に、その感情や感覚を表現するか、しないかの選択が可能になるとした。
変化の逆説〜ベイサーの「変化の逆説論」〜
ベイサーは、「変化の逆説論」で、「変化は人が自分自身である時に生じるのであって、自分自身であろうと努めている時には生まれない」と表現している。
今自分が行っている行為や行動を改めて「もっと良い行動」「もっとより人間らしい行動」をしようと目標を置くが、そのような努力は自己否定の上に成り立っているために、決して成功しない。「今の自分」を本当に受け入れた時に変化は自然に起きてくるというのが、「逆説的な変容の理論」。
神経症のメカニズム(コンタクト・バウンドリーの障害)
<Projection(投影)>
投影とは、自分が感じていることを他人の感覚に委ねてしまうこと。私が怒っているのにそれを認めない代わりに「あの人が私を怒っている」と自分の怒りを投影すること。自分の責任を負わないこと。
百武さんの追加説明は、「自分の感覚を分離してしまうこと、と言い換えてもいい。自分がそれに気づかない状態であることを言う。」でした。スピリチュアルが好きな人が陥りやすいとも。
<Introjection(鵜呑み)>
鵜呑みとは親の価値観や社会の価値観を無意識に取り入れてしまった状態。
<Retroflexion(反転行為)>
怒りは生きるためのエネルギーであるのに、表現しないで自己の内面に押し込めてしまうと、この感情は自分を傷つけてしまう。
<Confluence(無境界)>
自己と他者に境界線を持つと言う意味では「融合」と訳すよりは「無境界」の方が適切。生まれてきた赤ん坊は母親と境界線を持っていない。愛情は他者と融合した無境界の状態から始まるのである。子どもが成長するに従って自分の存在と他者の存在の違いを認識し境界線を引くことが自立することである。
<Deflection(話題転換)>
話題の転換や問題をずらしてしまうこと。核心に触れないようにするために「転換」する。
今日は、午前5時半の「お勤め」から一日が始まりました。さて、今日はどんなことになりますやら…。楽しみです。
関連エントリー
-
 読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
「不登校」のそのあとは?
コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休






















