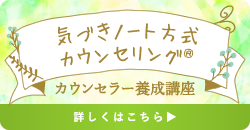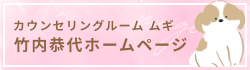- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 長田弘の詩
- 遊びを失う〜長田弘の詩「あのときかもしれない 三」〜
遊びを失う〜長田弘の詩「あのときかもしれない 三」〜
2018/04/06
「あのときかもしれない 三」 長田 弘
大通り。裏通り。横町。路地。脇道。小道。行き止まり。寄り道。曲がり道。どんな道でも知っていた。
だけど、広い道はきらいだ。広い道は、急ぐ道だ。自動車が急ぐ。おとなたちが急ぐ。広い道は、ほんとうは広い道じゃない。広い道ほど、子どものきみは肩身が狭い。ちいさくなって道の端っこをとおらなければならないからだ。広い道は、子どものきみには、いつも狭い道だった。
きみの好きな道は、狭い道だ。狭ければ狭いほど、道は自由な道だった。下水があれば、きみはわざわざ下水のふちを歩いた。土手を斜めにすべおちる道。それも、うえから下りるだけなんてつまらない。逆に上るんだ。走って上るなら、誰だってできる。きみはできるだけゆっくり上る。ずりおちる。
白い石塀のうえも、道だった。注意さえすれば、自動車も犬もとおれない。それはきみと猫だけの安全な道だった。身体のバランスをうまくとって、平均台のうえを歩くときのように、きみは歩く。だが突然、きみは後ろから怒鳴られる。「どこを歩いてるんだ。危ないぞ」。その声にびっくりして、おもわずバランスを崩して、きみは墜ちる。きみは不服だ。「危ないぞ」だなんて、いきなり、それも後ろから怒鳴るなんて、危ないじゃないか。しかし、二どと石塀のうえの道は歩かなかった。
何でもない道だったら、小石をきれいに蹴りながら歩いた。石を下水に落とさず、学校から家まで、誰にも邪魔させずに蹴りつづけてかえったのが、きみの最高記録だ。どんな石でもいいわけじゃない。野球選手がバットケースからバットを択びだすときのような目で、きみは小石を慎重に拾う。丸くて平べったい石がいい。道をスーッと、かるくすべってゆく石がいい。気にいった石がきみの蹴りかたがまずくて下水に落ちると、きみは口惜しかった。
子どものきみは、道をただまっすぐに歩いたことなどなかった。右足をまえにだす。次に、左足をまえにだす。歩くってことは、その繰りかえしだけじゃないんだ。第一それじゃ、ちっともおもしろくもなんともない。きみはそうおもっていた。こんどはこの道をこう歩いてやろう。どんなゲームより、どんな勉強より、それをかんがえるほうが、きみにはずっとおもしろかったのだ。
いま街を歩いているおとなのきみは、どうだろう。歩くことが、いまのきみにはたのしいだろうか。街のショーウインドウに、できるだけすくなく歩こうとして、急ぎ足に、人混みのなかをうつむいて歩いてゆく、一人の男のすがたがうつる。その男が、子どものころあんなにも歩くことの好きだったきみだなんて、きみだって信じられない。
歩くことのたのしさを、きみが自分に失くしてしまったとき、そのときだったんだ。そのとき、きみはもう、一人の子どもじゃなくて、一人のおとなになってたんだ。歩くということが、きみにとって、ここからそこにゆくという、ただそれだけのことにすぎなくなってしまったとき。-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休