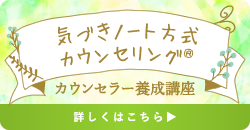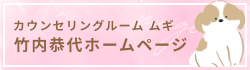- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- 長田弘の詩
- 私の「あのときかもしれない」を書き終えて
私の「あのときかもしれない」を書き終えて
2018/05/01
長田弘の詩「あのときかもしれない」がシリーズになっていると気づき、「一」から読み始めてすぐに、ゆっくりと、自分の内に何が想起するのかを見たくなりました。
それで、順番に取り上げていく、ことを思いついたのだけど。
そのときはまだ、どこに帰着するのかなど見当もつきませんでした。
けれど「七」を打ち込んだとき、父とのことが思い起こされて、ちょっと書くことを逡巡しました。
それで、「七」を書いてから「八」を書くまでに、時間が空いています。
どの回も、いつものコラムと違って、倍以上の時間…書き出してから書き終わるまで2時間余り掛かっているのですが、「八」は途中で涙が止まらなくなって、泣きながら書きました。
そのときに、「ああ、九は、父が亡くなったときのことだな」と気づきました。
これも逡巡してしまって、書き始めるまで少し時間が空きました。
「九」は、書き上げるのに2日掛かりました。
2時間半×2=5時間。
いえ、言葉を紡ぎ出すのに時間が掛かったわけではないのです。
気づいたら、ぼんやりと、私は、過去のその時間にトリップしていたのでした。
書き上げて、私は「モーニング・ワーク」(=喪の作業)をしていたことに気づきました。
父が亡くなって今年の夏で4年経ちますが、ゲシュタルトのワークで百武正嗣さんに扱ってもらった以外、ひとりで父のことを振り返ってみることはしませんでした。
百武さんにワークを行ってもらったことで十分満足していたのです。
ワークの中で、私は父に詫びることができましたし、父とのことは、私も悪いけど、私ばかりが悪いわけじゃないよね、というところで、私の気持ちは落ち着いていたので。
けれど、ワークを終えて時間が経って、私はもう少し違った声かけを、父にしたくなったのかもしれません。
最後のところがあまりに衝撃的で、そこばかりが自分の中でもクローズアップされるけど、本来は細やかで、穏やかな父の視線に包まれていたことも、私の記憶としてはあったので。
…鎮魂歌(レクイエム)を父に贈りたかったのかもしれません。
「九」も書きながら、涙が滂沱と流れました。
それで、…なんというか、こころの防波堤が決壊したようで、免疫力の低下を感じていたら、久しぶりに風邪を引きました。
咳き込んで、声が出なくなりました。
ホント、私の身体は分かり易い!と思います。
書くことは、私にとって生きること。
呼吸をするように自然で必要なこと。
そんなことを改めて感じたりしています。
読んでくださった方、長々とおつきあい、ありがとうございました。
あなたの中にも、あなたの「あのときかもしれない」が生まれていたら嬉しいなと思います。
画像は、朝の杏樹(アンジー)との散歩で見かけた、ご近所の玄関先に咲いていた、わすれな草。
青い色が優しげに揺れていました。
追記 そうそう。シリーズを書き上げたあと、私は父の姿や声を、容易に思い出せるようになりました。
関連エントリー
-
 映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」
もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの
-
 「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」
折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ
-
 「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」
折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ
-
 「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」
折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。
-
 「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」
折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休